
こんにyいは、けいみるるです。
今回は、ご飯茶碗の作り方~完成です。
ご飯茶碗とは、その名の通り、ご飯を盛り付けるための器です。
自分好みのご飯茶碗を作って見ませんか?
ご飯茶碗の成形
上から見たご飯茶碗

横から見たご飯茶碗

ご飯茶碗の削り

削ったご飯茶碗を真上からです。
素焼き

上から見た素焼き
釉薬掛け

上から見た釉薬掛け
ご飯茶碗の完成
天龍寺青磁
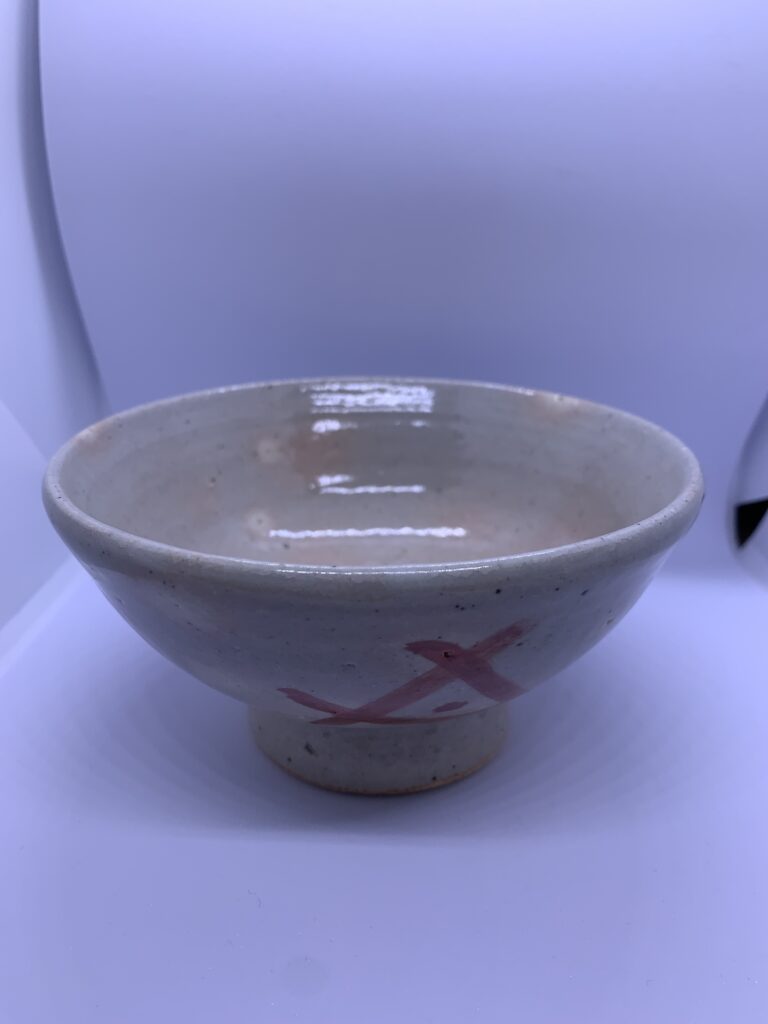
文様をかきました。

葉っぱの絵を描いています。
色々な釉薬

ご飯茶碗ですが、少し小さめです。
ご飯茶碗の作り方〜完成について書いていきます。
ご飯茶碗の作り方のポイントは
*ご飯茶碗の作る大きさの量を土取りをします。
*初めに直線的に土を引き上げてから、口の径を合わせてそこから腰を膨らませていきます。
*木こてを使うと指とは違い、指跡を消したり、形を整えることができます。
*茶碗ですので、腰から口縁に向かって斜めに引き上げていくのがポイントです。
アフィリエイト広告を利用しています。
ご飯茶碗の作り方
電動ろくろ

成形に使う道具のイラスト図
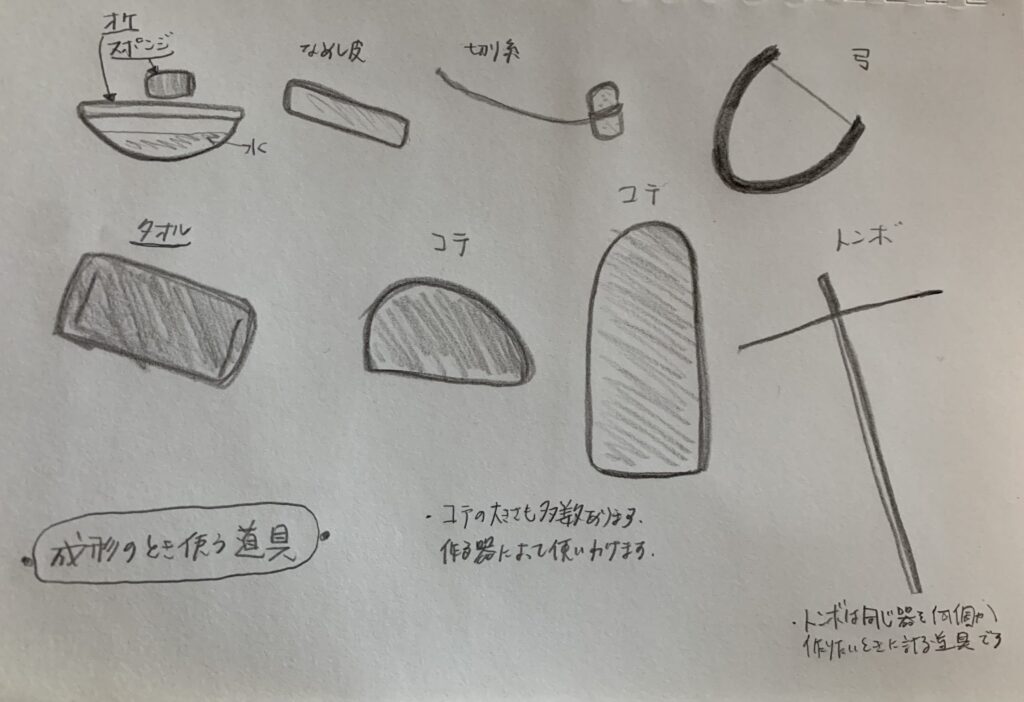
*成形については、器の作り方・成形とはを御覧ください。
ご飯茶碗の作り方の手順
①作りたい大きさの量の粘土を「玉取り」をします。
②両手で包むようにしながら中心を両手で親指で、穴をあけていきます。
③湯呑みのように直線に引き上げます。
④引き上げたら、底部分から徐々に横に広げていきます。
⑤ご飯茶碗は、中心から斜め横に上げていきます。
※だいたい、45度くらですね。
⑥底はしっかり指で絞めておきます。
⑦整えたい時は、コテを使います。
⑧丸い手のひらサイズのコテがいいと思います。
⑨内側の中心から、ろくろの回転にそって粘土を上げていきます。
⑩その時、外側にもう片方の手を添えるように一緒に動かします。
*添えないと、崩れてしまいます。
⑪上げ下げの時は、必ず、内側外側に手を同時に合わせます。
⑫ご飯茶碗の形にできましたら、最後に口元をなめし皮で整えます。
⑬底を多めにして指で印をつけます。
⑭切糸で切って板にのせたら完成です。
以上が、ご飯茶碗の作り方です。
ご飯茶碗の削りは
・乾燥させたら、削っていきます。
ご飯茶碗の削り
削る前の高台です。

削ったあとの高台です。

真上からのご飯茶碗

削りに使う道具のイラスト図
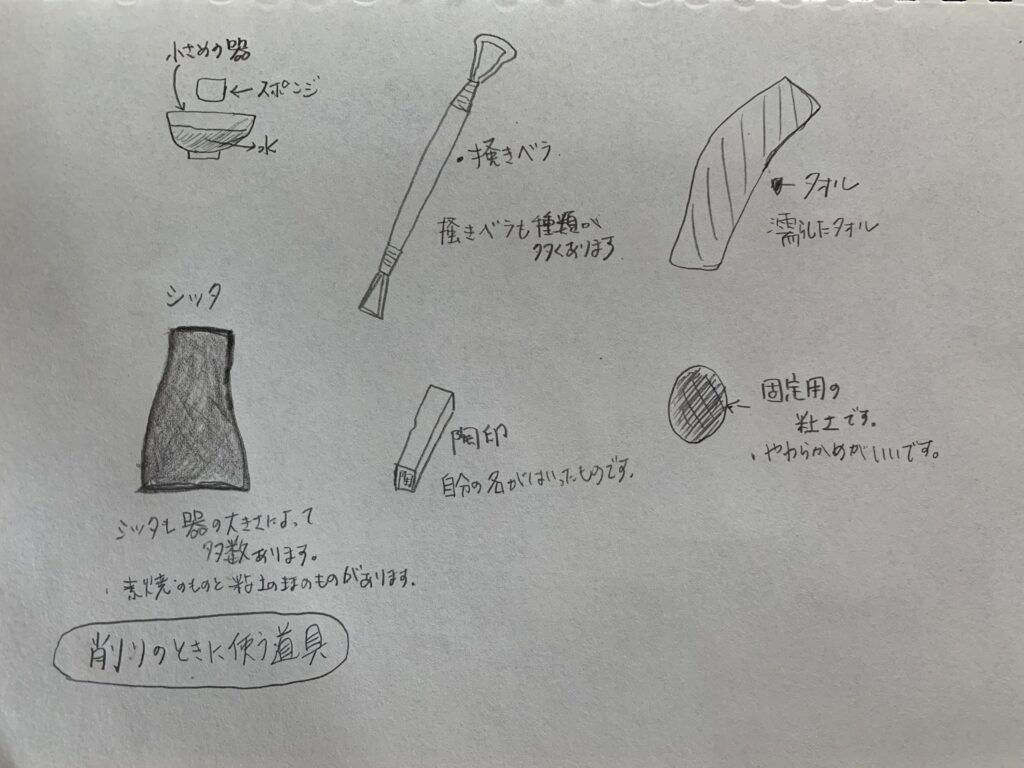
電動ろくろ
・削り方については、器の削りはどうやるのを御覧ください。
ご飯茶碗の削り方の手順
①ご飯茶碗は、ろくろにじかにのせて削りました。
②中心を出して三ヶ所にとめて固定します。
③底の部分を平らに削ります。
④腰の部分から口元までを削っていきます。
⑤全体を削って軽くします。
⑥高台を作ります。
・輪高台の形に削りました。
・他の器とは高さを出しています。
⑦削りが終わったら、スポンジで全体を拭きながら削った部分を整えます。
以上が、ご飯茶碗の削り方です。
ご飯茶碗の絵付け・釉薬は
素焼きは
表側

裏側

・乾燥させてから素焼きにしました。
・素焼きは削りの跡が残っていますので、全体をヤスリ掛けます。
・きれいになったら、スポンジで全体を拭き取ります。
・底を釉薬がつかないよう、撥水剤を塗ります。
絵付けは
・絵付けには、文様や葉っぱなどの絵を描いている器と、何も描いていない器があります。
釉薬掛けは
・絵付けした器には、絵が出るように天龍寺青磁を掛けました。
・絵付けしないものは、釉薬だけを掛けました。
茶マット・あめ釉・あめ釉+Baマット・そば釉・黄瀬戸釉を掛けました。
茶マット

あめ釉

あめ釉+Baマット

そば釉

黄瀬戸釉

絵付けをせずに、それぞれ違う釉薬掛けをしました。
1つだけ、2重掛けしました。
釉薬掛けをしたら、それぞれ底の部分に付いている釉薬をスポンジで拭き取りました。
プツプツ小さい穴を埋めました。
あまりこすると釉薬がはげてしまいますので、軽くこすりました。
以上が、絵付け・釉薬掛けになります。
本焼をして完成です。
まとめ
色んな、模様を描きました。
絵付けは楽しいですよね。
色々悩みます。
絵も上手く描けるように、練習したいです。
絵が描けたら、釉薬を掛けていきます。
絵なしもまたいいと思います。
色々試すのも楽しみの1つです。
釉薬も沢山種類がありますので、色んな釉薬を掛けたいですね。
そして、本焼きとなります。
どんなふうに焼き上がるか楽しみですね。
自分で作った器でご飯を食べてみると、また違う味を楽しめるのではないかと思います。
ぜひ、作ってみてはいかがですか?
参考になると嬉しいです。
最後まで見ていただきありがとうがざいます。
次回は、ぐい呑みの作り方です。
アフィリエイト広告を利用しています。



コメント