こんにちは、けいみるるです。
今回は、陶器の風鈴の削り方はです。
風鈴を成形したので、削れるくらいまで乾燥させました。
固くなりすぎたときは、濡らしたタオルで巻いておくと、柔らかくなります。
陶器の風鈴の削りの完成

上からの状態
本体と舌です。
2個ずつ作っています。
風鈴は軽くなるまで、削りました。
ある程度の重さはあります。
舌の方は、小さく穴をあけました。
1個目は、穴をもう一つあけようと棒でさしたら割れたので、1カ所のみあけています。
2個目は、両側にあけることができました。
アフィリエイト広告を利用しています。

陶器の風鈴の削り方を書いていきます。
陶器の風鈴の削り方の手順
電動ろくろ

風鈴を削る前

風鈴の削り途中

器の削り方については、器の削りはどうやるのをご覧ください。
風鈴の削り方の手順
本体をろくろで削ります。
風鈴は簡単に削れました。
形と重さを整えていきます。
①シッタは使わなくても削れますので、ろくろに直接付けます。
②ろくろを回して、中心をだします。
③中心がでたら、3ヵ所に固定用粘土で、はずれないように付けます。
④あまり重いと、吊るしたときに落ちる可能性があるので、軽めにします。
⑤全体的に削りました。
⑥高台はありません。
⑦最後に、削り痕をスポンジで、全体を拭き取ります。
削り後の作業
①風鈴のてっぺんの中心を、ポンスで穴をあけます。
②穴をあけた部分を、棒で軽く押し当てます。
③ひび割れ防止です。
④中側の底の部分に、自分の陶印を押します。
これで、削りが終わりです。
舌の部分
舌という風鈴を鳴らすものも作りました。
1つ目

上記の写真にある舌は、もうひとつ細い棒で穴をあけたのですが、ひび割れましたので、上の部分のみあけています。
2つ目

こちらは、2ヵ所に穴をあけることができました。
成形後に、穴を開けたほうが、割れにくいです。
あまり、固くなりすぎると、割れます。
その時は、濡らしたタオルにくるんで、柔らかくしてから、穴をあけるのがいいです。
削り終わったので、乾燥をしっかりして素焼きにします。
以上が陶器の風鈴の削り方でした。
まとめ
陶器の風鈴の削り方を書きました。
削りは、簡単に削れました。
1番注意したのは、軽くすることです。
吊るして飾るので、重いと落ちてしまう可能性を考えたからです。
軽さと、形を丸くするように、削りました。
これを、素焼きにしていきます。
毎回、素焼きにするときは、穴をあけたところのひび割れなどが心配です。
陶器の風鈴の削り方の参考になれば嬉しいです。
最後まで見ていただきありがとうございます。
次回は、陶器の風鈴の絵付・釉薬掛けはです。
アフィリエイト広告を利用しています。

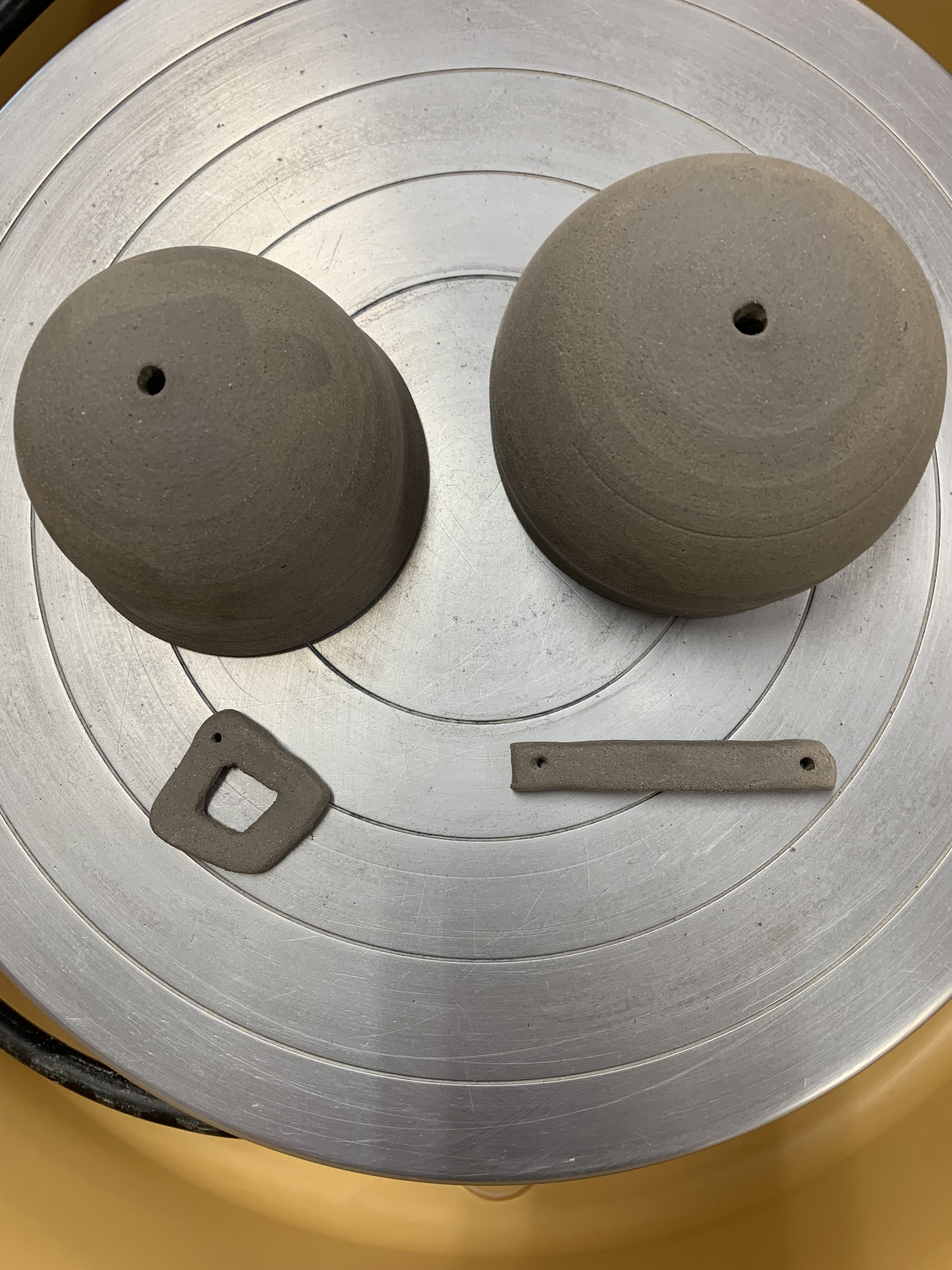


コメント