こんにちは、けいみるるです。
今回はそばセットの削りについてです。
そば猪口の高台

そば徳利の高台

薬味小皿の高台

そば皿の高台

そばセットの削りについて詳しく書いていきます。
そばセットの削りのポイントは
そば猪口・そば徳利・薬味小皿・そば皿です。
*高台を作っていきます。
*高台の種類については、器の底の高台の種類はを御覧ください。
そば猪口:
高台がありません。
碁笥底高台です。
そば徳利:
高台はこちらもありません。
碁笥底高台です。
高台がない方が安定します。
薬味お皿・そばを盛るお皿:
高台は一般的な高台です。
輪高台です。
すべて掻きベラで削っています。
これは使い勝手がいいです。
アフィリエイト広告を利用しています。

そばセットの削り方では
*削りについては、器の削りはどうやるのを御覧ください。
そば猪口
底を決めます。
高台は作りません。
糸底といって、高台がないことです。
成形時に糸でろくろから切り取った底部です。
形は碁笥底高台となります。
そば徳利
粘土のシッタを使いました。
口縁を注ぎ口を作り、胴体のところも凹みをいれています。
そのため、中心が出しづらいです。
多少のブレがあり、底の部分がいびつです。
これはこれで、個性というものになるかなです。
これもそば猪口と同じ高台のない碁笥底です。
薬味小皿
ろくろに直接のせて固定してます。
高台の位置を決めて腰から口元を削ります。
輪高台を作ります。
小さいので、すぐに削り終わりました。
そば皿
ろくろに直接固定します。
高台を決めて腰から口元まで削ります。
厚みがあるときは、軽くなるように削ります。
輪高台を作りました。
*削ったあとは、均等に削れているか触って確認します。
*持った時に重みがあったときは、軽くなるまで削ります。
以上が、そばセットの削り方でした。
まとめ
削るときは、中心に合わせていきます。
そば徳利は、口縁を歪めているのでろくろに直接置けませんので、粘土のシッタを使います。
そば猪口・薬味小皿・そば皿はろくろに直接固定して削れます。
成形した時に、切り糸で切り離して板に乗せると若干歪んでしまいます。
自然乾燥しますので、形がそのまま固くなります。
削る時にろくろで中心を出す時、若干ぶれますので注意が必要です。
中心が合わないと、均一に削れませんのでしっかりと合わせます。
これがさらに縮みます。
参考になれば嬉しいです。
最後まで見ていただきありがとうございます。
次回は、そばセットの絵付け・釉薬です。
アフィリエイト広告を利用しています。



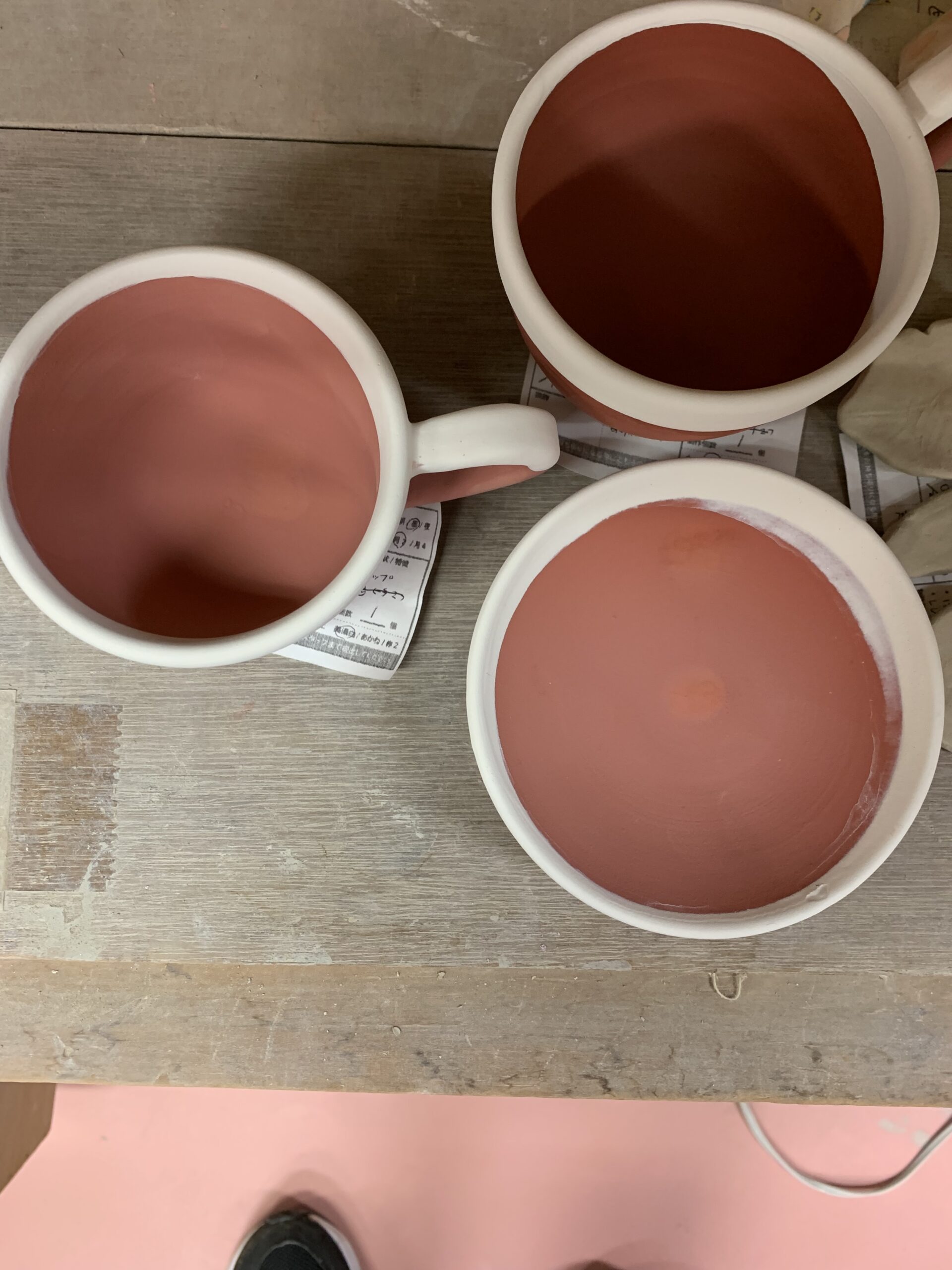
コメント