こんにちは、けいみるるです。
今回は、津軽焼とは何についてです。
津軽焼という焼物を知っていますか?
日本のどこにあるのでしょうか?
津軽焼の作品

津軽焼とは、
青森県弘前市で焼かれていた焼物です。
藩の御用窯として、日用品や調度品など幅広く焼かれていました。
釉薬に、りんごの木の灰を使って焼いています。
白と黒の釉薬を使っています。
白い釉薬に、りんごの木の灰を混ぜて使っているので、釉薬が重なっているところは「なまこ模様」といわれています。
東北地方
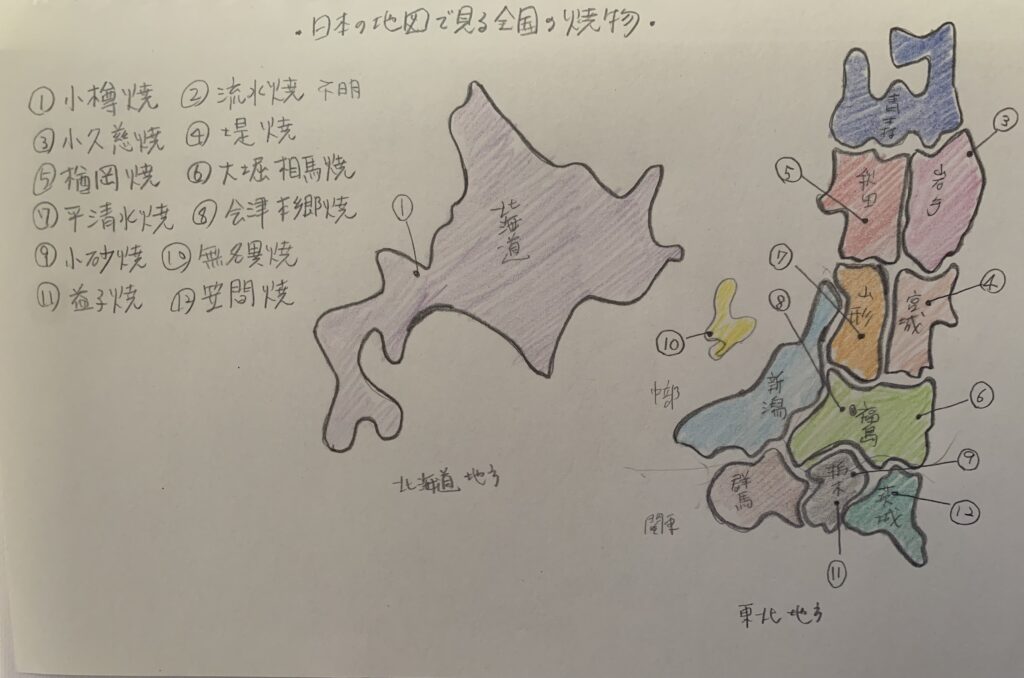
青森県弘前市
りんごの生産量日本一です。
桜の名所としてしられる、弘前公園・岩木山・岩木山神社・弘前城・レトロな建物が見どころです。
津軽焼とは何について書いていきます。
津軽焼の歴史・特徴・魅力は
津軽焼の歴史は
1697年に、津軽藩4代藩主信政によって、集められた陶工たちによって築いた、平清水焼・大沢焼・下川原焼・悪戸焼が源流です。
藩政時代は、主に津軽藩の調度品や日用雑貨が焼かれていました。
明治時代は、鉄道の開通によって、他県の焼物が流入し、その地位を奪われました。
大正時代では、一時途絶えてしまいました。
昭和に入ってから、再興されました。
津軽焼の特徴は
りんごの木の灰を混ぜています。
白と黒の釉薬・釉薬を使わない自然釉・素朴な風合い、そして手作りという温かみがあります。
釉薬が重なったときにできる、「なまこ模様」・燃料の灰が作る「胡麻」などの模様もあります。
津軽焼の魅力は
使うほどに味合いが増すことと、経年劣化によって表情の変化が見られます。
無駄のないシンプルさがあります。
伝統工芸品です。
津軽焼の本物と偽物の見分け方
本物
光を通さない・ザラついた肉厚な質感です。
刻印や窯印が施されています。
偽物
古い陶器の様式からかけ離れたデザイン・制作時期にそぐわない作風がみられます。
不自然で、ギラギラしていたり、色や光沢にムラがあります。
磁器のようなツルりとした表面である場合です。
この点を参考に見分けてみるのもいいですね。
どうしても、不安なときは、専門家にみてもらうがいいですね。
津軽焼の今は
現在で伝統を守り続けています。
地元の土を使って、釉薬に黒天目釉やりんごの木の灰を、原料とするりんご釉を使うのが主流です。
販売もされています。
津軽茶道美術館
津軽焼を所蔵・展示されています。
以上が、津軽焼とは何でした。
まとめ
津軽焼とは、青森県弘前市を中心に焼かれていた焼物です。
1697年前と歴史は古いです。
津軽藩が陶器の自給自足を目的としたことが起源です。
その後には、「大沢焼」「平清水焼」「下川原焼」「悪戸焼」の4つの窯で焼かれていた焼物の総称が津軽焼となったのです。
明治時代では、一時的に途絶えたものの、昭和の時代には復興しました。
りんごの木の灰を使った釉薬を、作り出したのはすごいですね。
色合いがとても素朴で温かみを感じます。
職人の手作業で一つ一つ心がこもった焼物ですね。
本物を見てみたいです。
津軽焼鑑賞の参考になればうれしいです。
最後まで見ていただきありがとうございます。
次回は、鍛冶丁焼とは何です。
アフィリエイト広告を利用しています。



コメント