こんにちは、けいみるるです。
今回は手ろくろの使い方についてです。
手ろくろという道具を知っていますか?
使い方は?
陶芸といえば、手ろくろが思い浮かぶのではないでしょうか。
初心者の方には、見慣れたものですね。
手で回しながら、器を作る使い方になります。
手ろくろ

手ろくろとは
手ろくろとは、手動で回しながら成形するものです。
手びねりともいわれています。
円形の台で、直径18〜45cmぐらいのものまであります。
絵付をするときにも使います。
初心者の方によく使われます。
紐作り・玉作りがあります。
手ろくろは指先を使って粘土を、伸ばしながら形を作ります。
手ろくろも色々な作品が作れます。
湯呑・茶碗・マグカップ・小鉢・お皿など作ることが出来ます。
アフィリエイト広告を利用しています。
手ろくろの使い方について書いていきます。
手ろくろの使い方
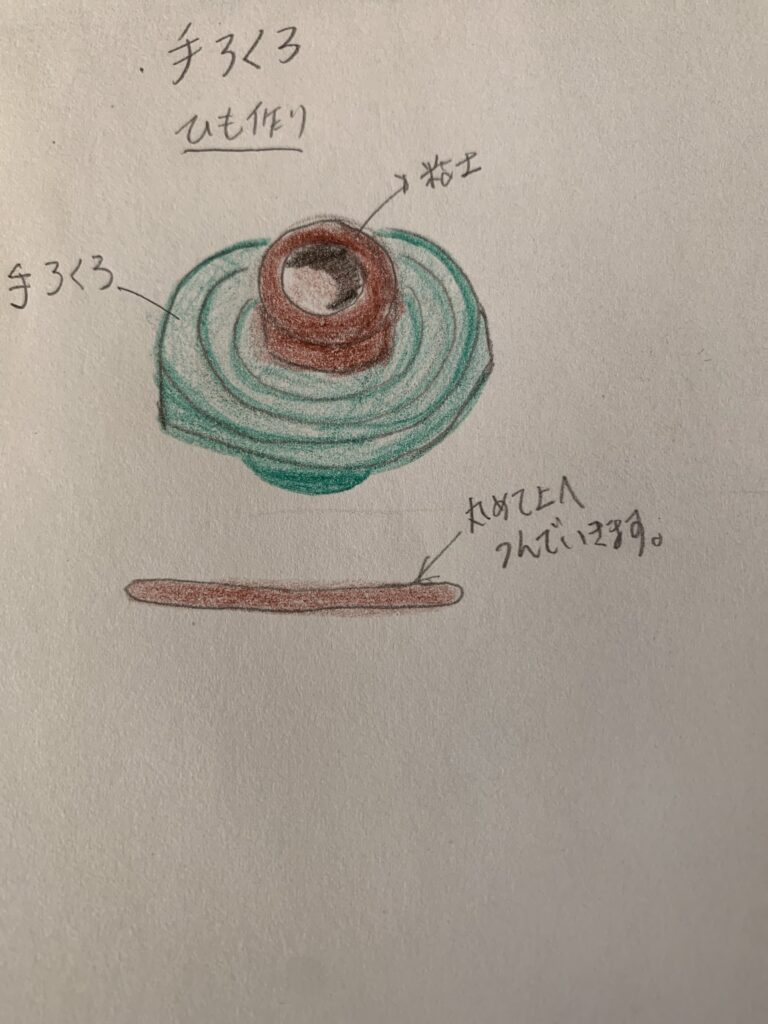
紐作り:粘土を紐状に伸ばして1段ずつ、積み上げて作る方法です。
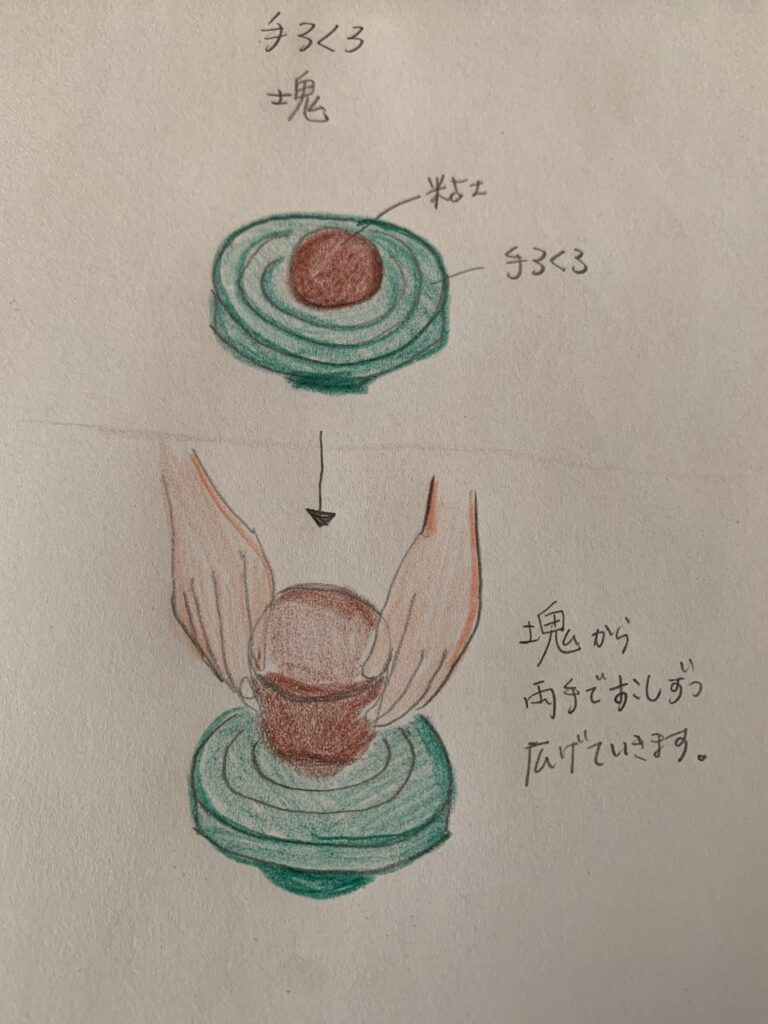
玉作り:粘土の量100g・200gと作る粘土の量を、丸めて塊にしたもので作る方法です。
この方法は、器だけでなく人形やどんな動物なども作ることが出来ます。
手ろくろは自分で形にしていきます。
手ろくろで作るときのコツは、粘土を両手の指先で寄せながら積んでいくと、自然に立ち上がっていきます。
手で作るろくろは電動ろくろと違い、水を多くは使いません。
粘土は使わないときには、濡らしたタオルにくるんで置きます。
乾きすぎると、ヒビが入ってしまいます。
常に湿らせておくようにします。
手ろくろで気をつけたいことは乾燥だけではなく、空気が入らないようにすることです。
空気が入ってしまうと、焼いたときに割れてしまうからです。
手ろくろでも、成形の前は「荒練り」・「菊練り」をして粘土をしっかりと練ることが重要です。
練ることは、空気を抜いて、粘土の固さを均等にしていくのが目的です。
せっかく作った作品を、空気が入ったことで割れてしまうなんて、とても悲しいですよね。
どんなときでも、粘土をしっかり練るのはとても意味があり重要です。
手ろくろは、大・小と種類もあります。
ほとんどは小の方を使うことが多いです。
作りたい大きさによって使い分けています。
手ろくろの重さは3〜4kg位と重たいです。
使うときには落とさないよう注意が必要です。
色は緑色が多いです。
場所は取りません。
使った後は、粘土が付いているので、雑巾などで拭き取ります。
乾いてくると、こびりついて取りづらくなります。
お手入れも必要です。
手ろくろのデメリットとしては、
電動ろくろとは違い、作業スピードが遅いです。
手動のため、連続して回し続けなければいけないので難しいです。
複雑な作品作りには不向きなときがあります。
以上が、手ろくろとはでした。
まとめ
手ろくろとは手で回しながら作る手動のものです。
重さがありますので、足元などに落とさないように気をつけましょう。
手ろくろには粘土を細長くして紐にして作るものと、粘土を丸めて塊にして作る方法があります。
一日体験ではよく見かけます。
手で回していくので、回転が止まってしまいます。
均等に粘土を上げるのも、大変だと思います。
これも慣れてくればできるようになりますので、たくさん練習するしかないですよね。
器だけではなく、置物や人形なども作れます。
作りたいものを考えるのも、楽しいですよね。
器や置物にも挑戦してみては、いかがでしょうか。
手ろくろをつかうときの参考になれば嬉しいです。
最後まで見ていただきありがとうございます。
次回は、手ろくろ・湯呑みの作り方です。
アフィリエイト広告を利用しています。



コメント