こんにちは、けいみるるです。
今回は、温泉津焼とは何についてです。
湯泉津焼という焼物を知っていますか?
温泉津焼

温泉津焼とは、
島根県太田市温泉津町で焼かれています。
地域のブランドです。
耐火性の高い石見粘土を使っていて、高温1300度の焼成するため、硬く焼き上がり割れにくいのが特徴です。
中国地方
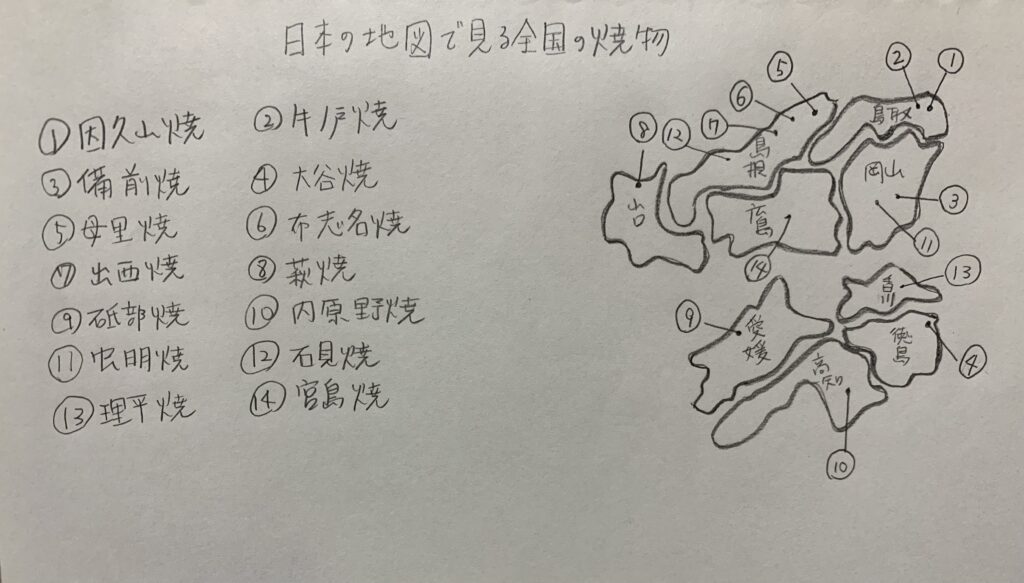
島根県大田市温泉津町
古き良き時代の風情が残る温泉街です。
歴史的な町並み・温泉があるのが魅力の街です。
温泉津焼とは何について書いていきます。
温泉津焼の歴史は
300年以上の歴史があります。
1704年、江戸時代に始まりました。
登り窯で、主に「半斗」と呼ばれていた水瓶を焼きていました。
日本全国に出荷していました。
第二次世界大戦後は、プラスチックにおされ衰退していきました。
現在、窯は再興されています。
温泉津焼の特徴・魅力は
耐火性の高いです。
高温で焼成のため硬くて割れにくいです。
青色「呉須」と赤色「辰砂」の色味があります。
温泉津焼の粘土
石見粘土を使っています。
温泉津焼の釉薬
黄緑がかった色合いと艶があります。
手に持つとずっしりと重みがあります。
存在感のあるやきものです。
日用の陶器の産地として発展していました。
温泉津焼の今
毎年、春と秋には「やきもの祭り」が開催されています。
登り窯に火がはいります。
やきもの館前や窯元でのやきもの即売会も賑わっています。
現在窯元は3軒残っています。
椿窯・椿窯・森山窯が伝統を守り続けています。
まとめ
温泉津焼は、島根県大田市温泉津町で焼かれていたや焼物です。
水瓶「はんど」が全国的に有名になりました。
耐火性の高い石見粘土を使っています。
高温1300度で焼成するので、硬くて割れにくいのが特徴です。
現在は、3軒ほどが残っていて、伝統を守り続けています。
歴史が長い焼物です。
温泉津焼の散策に出かけてみたいですね。
焼物を散策し、疲れた体を温泉で癒やせたら言う事無しですね。
参考になれば嬉しいです。
最後まで見ていただきありがとうございます。
次回は、こぶ志焼とは何です。
アフィリエイト広告を利用しています。


コメント