
こんにちは、けいみるるです。
今回は、楊枝入れの削り方についてです。
楊枝入れの削り
本体・蓋

楊枝入れの成形のあと乾燥させたら削ります。
固くなりすぎていたので、濡らしたタオルに作品を巻いてしばらく置いておきました。
それぞれ、外と中を削りました。
蓋はたくさん削り、軽くなりました。
素焼きはどんな感じになるのかです。
楊枝入れの削りを書いていきます。
楊枝入れの削り方
電動ろくろ
器の削り方については、器の削りはどうやるのを御覧ください。
本体の削り
①内側が見えるようにして置いて、ろくろにて中心を出します。
②中心がでたら固定用粘土で固定します。
②中側を掻きベラで上から下に削ります。
①今度は、底の部分を削るため、中心をだして固定します。
②外側も掻きベラで底の部分を平行になるように削ります。
③高台の中側を削ります。
④丸みのある高台を作りました。
固定用の粘土はすぐに乾いてきます。
その都度、濡らしたタオルで巻いておきます。
蓋の削り
①中側を削るために内側を上にして、中心をだして固定します。
②掻きベラで中を削ります。
③次に、一度固定用粘土を外して底の部分の中心をだして固定します。
④高台は作らずに、丸みを出しました。
上記の写真が削りの完成です。
持ったときに軽くなるまで削りました。
楊枝をいれるので、本体と蓋はピッタリしないほうがいいですね。
素焼きにしますが、ひび割れなどないことを祈るばかりです。
以上が、楊枝入れの削り方でした。
まとめ
楊枝入れを削りました。
本体と蓋をそれぞれ削りました。
途中、室内が温かいので固定用粘土がすぐに乾いてきて、外れてしまうことが何度かありました。
その都度、粘土を濡らしたタオルにくるんで使いました。
楊枝入れの削りがうまくいかなかったら、ぐい呑にしようかと思いましたがなんとか出来ました。
楊枝入れも、初めて作りました。
皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。
楊枝入れの削りのときに、参考になれば嬉しいです。
最後までみていただきありがとうございます。
次回は、楊枝入れの釉薬掛けについてです。
アフィリエイト広告を利用しています。


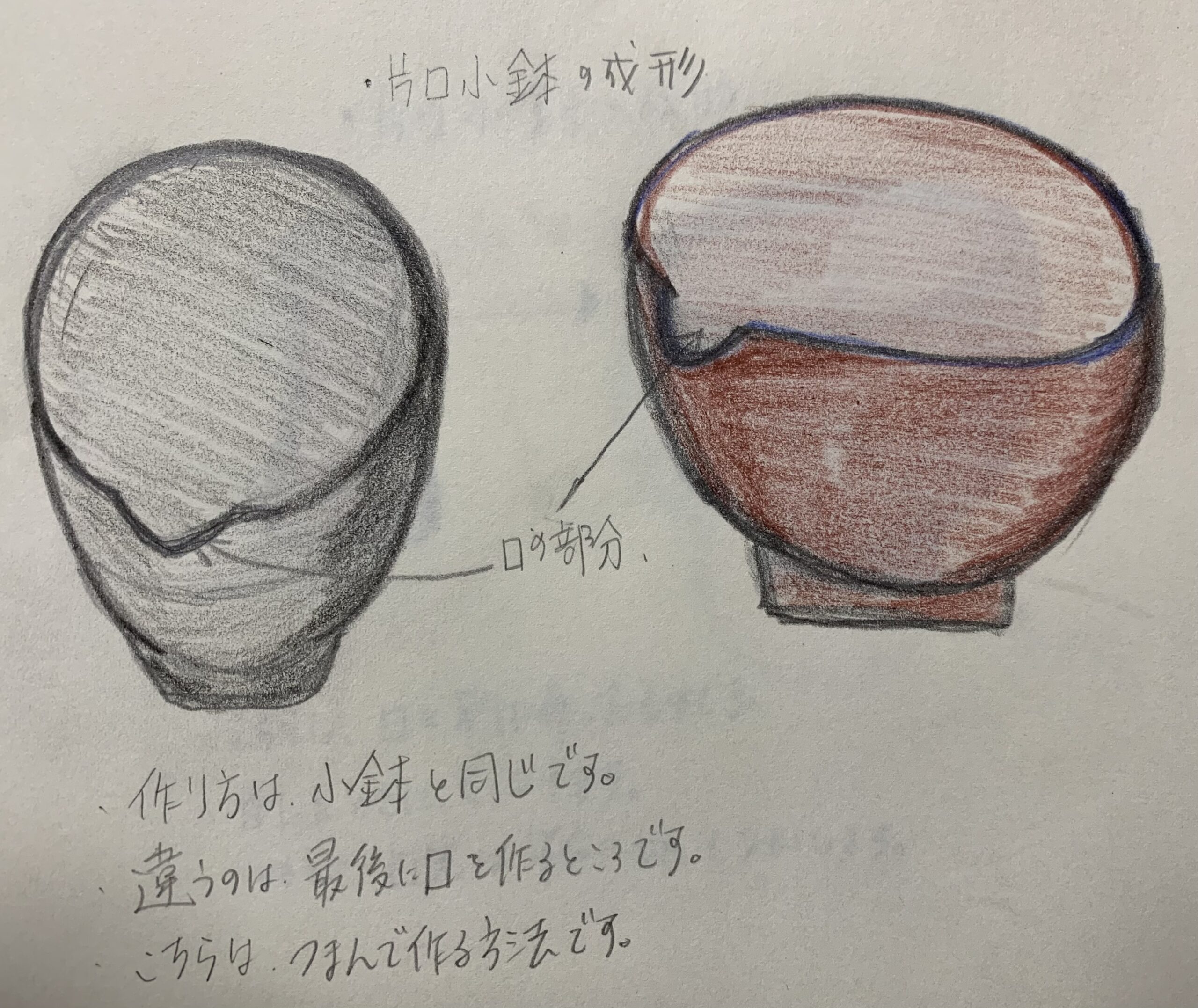
コメント