
こんにちは、けいみるるです。
今回は、陶器:ワイングラスの釉薬掛けはについてです。
陶器のワイングラス
素焼き

スリムの部分が短いもの

スリムの部分が長いもの
釉薬掛け

唐津白濁長石釉+黒マット

キヌタ青磁+黒マット

全体に掛けずに、下の部分は素焼きのままで本焼にしました。
どんな色合いになるでしょうか?
アフィリエイト広告を利用しています。

陶器:ワイングラスの釉薬掛けはを書いていきます。
ワイングラスの釉薬掛けのポイントは
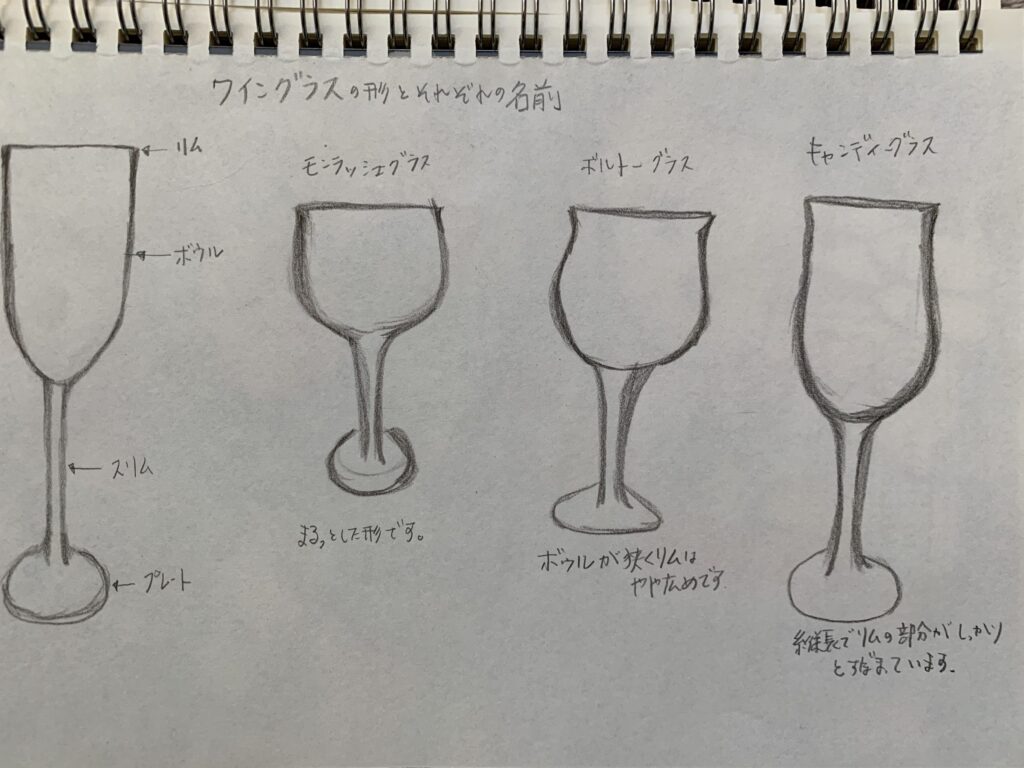
*ボウルといわれる本体部分に釉薬をかけます。
*2個のワイングラスがありますので、それぞれ違う掛け方をしました。
*1個は全体に掛けていきます。
*もう1個は、スリムと呼ばれる部分の半分くらいまでかけて、その下のプレートまでは素焼きのままにします。
ワイングラスの釉薬前の準備は
素焼きになった器には、
削り跡などがついていますので、ヤスリかけをしていきます。
ザラザラした部分だけではなく、全体をヤスリかけしていきました。
ヤスリかけが終わったら、スポンジで全体を拭き取ります。
高台の部分には、撥水剤を塗りました。
釉薬が底につかないようにです。
ワイングラスに釉薬を掛ける
1つ目は
唐津白濁長石釉+黒マット
ハサミを使って掛けます。
釉薬に引っ掛けないようゆっくりと外します。
乾いたところをはさんで板にのせます。
2つ目は、
キヌタ青磁+黒マット
手でスリムの部分をもって掛けます。
本体全体と手で持つ部分、スリムとプレートといわれる部分は、釉薬を掛けずに素焼きのまま本焼にします。
釉薬を掛けたら、
プツプツしているところを、指でこすって埋めます。
二重掛けの1つは、キヌタ青磁は乾きが遅く、プツプツは埋められませんでした。
高温で焼ますので、溶けて流れていくと思います。
スポンジで底の部分についた釉薬を拭き取ります。
本焼していきます。
以上が、陶器のワイングラスの釉薬掛けでした。
まとめ
ワイングラスの釉薬は、2種類掛けました。
それぞれ、違う釉薬をかけていますが、その上に掛けた釉薬は2つともに黒マットです。
どんな色に仕上がるのか楽しみです。
ワイングラスの釉薬掛けの、参考になればうれしいです。
最後まで見ていただきありがとうございます。
次回は、ワイングラスの完成です。
アフィリエイト広告を利用しています。



コメント