こんにちは、けいみるるです。
今回は陶芸の原料・型作りについてです。
陶芸の原料が何か知っていますか?
陶芸では、型で作れることを知っていますか?
陶器の粘土

磁器の石

陶芸の原料とは、
陶器は、粘土50%・珪石40%・長石10%などの土の材料とそれを焼くための釉薬の材料です。
「土物」といいます。
磁器は、鉄分の少ない原料、陶石という石を砕いたものです。
型作り(鋳込み)

陶芸の型作りとは、
石膏などの材料で作られた型を使って、粘土を成形する方法をいいます。
泥漿(液状の粘土)を流し込んで形を成形します。
アフィリエイト広告を利用しています。
陶芸の原料・型作りについて書いていきます。
陶芸の原料とは
陶器は、長石10%・珪石40%・粘土50%です。
磁器は、鉄分の少ない、カオリナイト・陶石を使います。
型作り(鋳込み)=石膏型とは
泥漿を型に流し込んで成形します。
石膏型で出来ています。
鋳込みともいわれています。
陶芸の原料・釉薬は
表面に掛ける釉薬の原料は、灰・金属・土です。
植物の灰は珪酸を含んでいます。
高温で焼かれるとガラス化しいて、釉薬になります。
金属・土を混ぜて、色や熔け具合を調整します。
焼物の原料で作ることが出来るのは、人口の歯や骨・コンピューターの回路基盤・プラスターなどの切削工具があります。
成形から本焼きまで焼物は収縮していきます。
一般的に土は5〜20%位縮みます。
収縮があまり大きい土は変化しやすく、使いにくくなります。
収縮しない土は焼き締まらないので割れやすく、焼いても耐えられません。
焼物を高温で焼く目的は、土を固くするためと、灰を熔かして釉にするためです。
焼物の高温焼成は一般的に1250℃になります。
土に含まれる”結晶水”といわれている水分が、飛ぶ温度が270℃です。
土に変質して素焼化する温度が570℃です。
土や釉薬のガラス質に成分である珪酸が、純度の高い状態で熔ける温度が1700℃です。
型作り=石膏型は
型作り=石膏型は、塑像を作るときと同じように、粘土でいったん作った形を、石膏で型取りしておけば、同じものを大量に複製できます。
塑像とは、可塑性のある軟材を使って形成された立体造形のことです。
泥状を型に流し込んで成形する “鋳込みの成形”のことをいいます。
型を使っての成形技法です。
複雑な形状は石膏型のいくつかの断を組み合わせます。
工場で大量生産されている食器などはこの型取りで作られています。
石膏型は市販で売っています。
自分で作ることもできます。
アフィリエイト広告を利用しています。
石膏型=鋳込み(いこみ)成形
古くから陶磁器の成形に使われてきた手法です。
型の内側に泥漿調整を行った陶磁器土の層を、一様につくる成形方法です。
陶磁器土はあらかじめ、解膠剤と、水によって適正な作業性を有する状態に調節しておきます。
器だけではなく、人形や動物や植物なども、石膏型で作れます。
大量生産にも対応できます。
中空の成形ができるのも特徴です。
鋳込みには2種類があります。
鋳込み
一般的な鋳込み:
・石膏型に泥漿を流し込む方法です。
圧力鋳込み:
・泥漿を流し込んで圧力をかけて、石膏型の隙間で成形出来る方法です。
*これはろくろで引かずに型を取ることで作品ができます。
*ろくろで作れない複雑な形が、泥漿を流し固めただけで作れます。
*自然乾燥したら削ります。
*削りはろくろ成形のときと同じです。
*石膏型はうまくやらないと、外れにくくなります。
*珪酸ソーダや解膠剤が多すぎたことや石膏型が濡れずていることや、出来上がったばかりの石膏型を使ったことなどが原因があり中々難しいですね。
以上が、陶芸の原料・型作りとはでした。
まとめ
陶芸の原料・型作りでした。
焼物の原料や高温で焼く目的などがあります。
陶芸はろくろだけではなく、石膏型でも作ることが出来ます。
石膏型で作ったことはありませんが、昔工房にいた時に石膏型を使って、花瓶や干支の置物などを作っていました。
少しだけ手伝ったような気がします。
石膏型を使って置物に挑戦したいですね。
参考になればうれしいです。
最後まで見ていただきありがとうございます。
次回は、陶芸の素地の加工です。
アフィリエイト広告を利用しています。
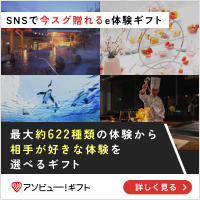


コメント