
こんにちは、けいみるるです。
今回は、急須の削り方についてです。
急須の削り

バラバラだったパーツを取り付けました。
実際作ってみると、難しかったです。
急須の組み立ては
バラバラなパーツを組み立てていくので手間暇がかかります。
削りと取り付けるのとで、時間がかかりました。
注ぎ口と取っ手の部分です。
蓋は、微妙に合わないので、素焼きにしてからヤスリでこすりながら、あわせられたらなと思います。
本体と合わせるのに2週分かかっています。
ひたすら削っては合わせてみるを繰り返しました。
急須を作って見て思うのは、他の器と違い時間がかかるとこです。
急須の削り方について書いていきます。
アフィリエイト広告を利用しています。
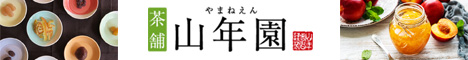
にほんブログ村
急須のそれぞれのポイント
・蓋物は合わせる部分をしっかり作ります。
・蓋の方が本体より少し口の径が小さくなります。
・削りながら蓋と本体を微調整していきます。
・乾燥時と本焼きの時には、蓋をかぶせておかないとゆがんで蓋が合わなくなります。
・注ぎ口と持ち手の角度はだいたい85度から90度くらいが注ぎやすいといわれています。
急須の削り方
削り方については、器の削りはどうやるのを御覧ください。
本体の削り
①全体的に削ります。
②高台を作ります。
③底の部分は安定感を重視するのであれば、高台は作らずに碁笥底高台にします。
蓋の削り方
①蓋を削る時は、シッタに蓋の上を下にして固定します。
②中心に指をのせる浅い穴をあけます。
③外側をぐるりと平らに削り取ります。
④本体の口径にはまるように、蓋の合わせ部分を削りだします。
茶こしの作り方
①注ぎ口の部分を切り取ります。
②別で作った茶こしが本体と合うか、はめてみます。
③切り取った口の部分にドベを塗ります。
④茶こしをはめ付けて、はみ出している粘土は切り取ります。
⑤茶こしに小さい穴を開けていきます。
※穴の数は多いほどお茶の出がよくなります。
※ロート状になった茶こし用のポンスを使うと穴が均等に開けられます。
注ぎ口の付け方
①本体と茶こしの部分に、注ぎ口を合わせていきます。
②注ぎ口をつける部分に、ドベをつけていきます。
③そこに注ぎ口を付けて、合わせ目の所をよくなじませます。
④はみ出したドベは拭き取ります。
把っ手の付け方
①持ちての部分を決めます。
②持ちやすい角度に本体につけていきます。
③付けたところは外れないようにします。
※把っ手は、取り付けるときの角度が重要です。
※注ぐときの手首を返しやすいようにすることです。
全て削ることができれば、それぞれを本体に付けていきます。
ドベを付ける部分と本体に塗って、それぞれのパーツが外れないようにしっかり押し付けます。
完成したら、乾燥して素焼きにしていきます。
以上が、急須の削り方でした。
まとめ
急須の削り方を書きました。
取っ手は、持ちやすい角度がポイントです。
急須は、尻漏れやすすぎやすいのが重要です。
取っ手を付ける位置は、口の部分と同じ高さです。
角度は、生活様式によって違いがあります。
の生活なら深い角度がいいのと、テーブルで使うなら浅い角度がいいです。
急須は実際作ってみて一番難しいと思いました。
出来上がった時には、達成感がありました。
難しいものでも挑戦していきたいですね。
急須の削るときの参考になれば嬉しいです。
最後まで見ていただきありがとうございます。
次回は、急須の釉薬の掛け方です。
アフィリエイト広告を利用しています。




コメント