
こんにちは、けいみるるです。
今回は、土鍋の作り方についてです。
例)土鍋の写真

土鍋とは、
日本の伝統的な調理器具です。
陶芸で作ることができます。
電動ろくろで作ります。
土鍋は小さいものから大きなものまで、形はさまざまあります。
土鍋を作る粘土には、
ペタライトというリチウム長石が入っているものを使います。
特徴は、熱膨張が非常に低く、急熱急冷に対して強いです。
粘土に30%入っています。
近年、ペタライトの入手が困難となっているため、価格が高騰しています。
ジンバブエが主産国です。
アフィリエイト広告を利用しています

土鍋の作り方を書いていきます。
土鍋の大きさ
*サイズは大体の大きさであり、物によって異なります。
①1人:直径約18〜22.5cm・容量約0.65L 5号
②1〜2人:直径約20〜22cm・容量約1.5L 6号 7号
③2〜3人:直径約23〜25cm・容量約2.2L 8号
④3〜4人:直径約26〜28cm・容量約3.2L 9号
土鍋の作りのポイントは
※土鍋は蓋をするので、本体には口元に蓋を乗せる台を作ります。
※蓋と本体を測ります。
※持ち手も別に作っておきます。
土鍋作りの注意点
土鍋をつくる粘土は、砂っぽく少し挽きにくい粘土です。
保温性も大切なので、薄く挽きすごないようにします。
土鍋の作り方
土鍋のイラスト図
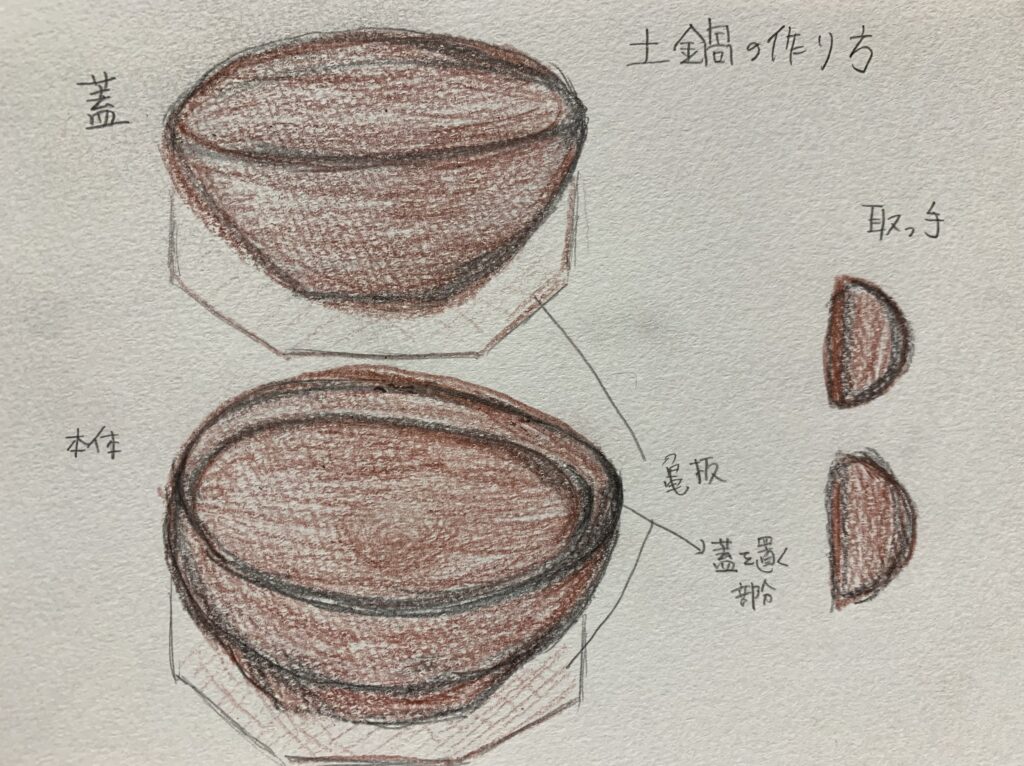
イラストはイメージです。
電動ろくろ
成形の作り方については、器の作り方・成形とはを御覧ください。
※作る大きさによってですが、3人〜4人以上の場合は、亀板を使うと形を崩すことなく外せます。
※亀板の使い方については、陶芸・亀板の使い方をご覧ください。
※土鍋など直接火にかける器は、耐熱土用の粘土を使います。
※ペンライトというのがはいっている粘土があります。
土鍋の作り方の手順
本体
①亀板を設置します。
②好みの大きさの塊(3kg〜4kg)を中心に置いて、土ころしをして芯をだします。
③中心がでたら上面を平らにします。
④手の指全体を使って、中心に穴を開けて広げます。
⑤底に近づいたら、右手で左に押し広げて見込みを広くしています。
※底の部分は厚めにとっておきます。
⑥大皿を作るように側面を挽き上げたり、引き伸ばしたり形を決めていきます。
⑦粘土を均等にしたいとき、整えたりするには、木コテを使っていきます。
⑧口元の部分には、蓋のかかりを作るために溝を作ります。
⑨右手人差し指で口元を押し込んで溝を作ります。
⑩外側を抑えながら上の部分に段差をつけます。
※口径は、一番広い中心で測ります。
⑩口元が細くならないように、バランスよく作ります。
⑪形や口元の台の部分が完成したら、なめし皮で整えていきます。
⑫底の部分を切り糸で切ります。
⑬板に移しますが、亀板の場合は切ってそのままろくろから外します。
次に蓋を作ります。
大きい場合は、亀板を使います。
土鍋の蓋の作り方の手順
①本体より2kgの塊を中心におき、土ころしをして見込みを広げていきます。
②数回に分けて、鉢の形に挽き上げます。
③口元をなめし皮で一度締めます。
④口元を倒して広げます。
⑤本体の口元のかかりに収まるように測ります。
⑥丸い形のコテで、形をきれいに仕上げていきます。
⑦最後に、口元を整えます。
⑧底の部分を切り糸で切っておきます。
取っ手の部分をつくります。
取っ手の作り方
※蓋の部分と、本体の両側の部分です。
①粘土を土ころしします。
②土取りをして、中心を穴を開けていき斜めに引き上げていきます。
③口元を太く、丸みを残します。
④形を整えて口元をなめし皮で仕上げます。
※色々な形に作っておくといいですね。
すべて作れたら、削れるくらいまで、乾燥させていきます。
以上が、土鍋の作り方でした。
まとめ
今回は土鍋の作り方を書きました。
蓋と合わせるのが難しいところです。
まだ作ったことはありませんが、いつか挑戦しようと思います。
いい土鍋が作れるようになりたいですね。
土鍋作りの参考になればうれしいです。
最後までみていただきありがとうございます。
次回は、土鍋の削り方です。
アフィリエイト広告を利用しています。



コメント