こんにちは、けいみるるです。
今回は、相川焼とは何についてです。
相川焼という焼物を知っていますか?
どこの地方の焼物でしょうか?
相川無名異焼

相川焼とは、
佐渡焼ともいわれています。
赤みのある煎茶器など日用粗陶製品が多いです。
相川無名異焼ともいわれます。
無名異土を使っているため、相川無名異焼ともいわれます。
東北地方
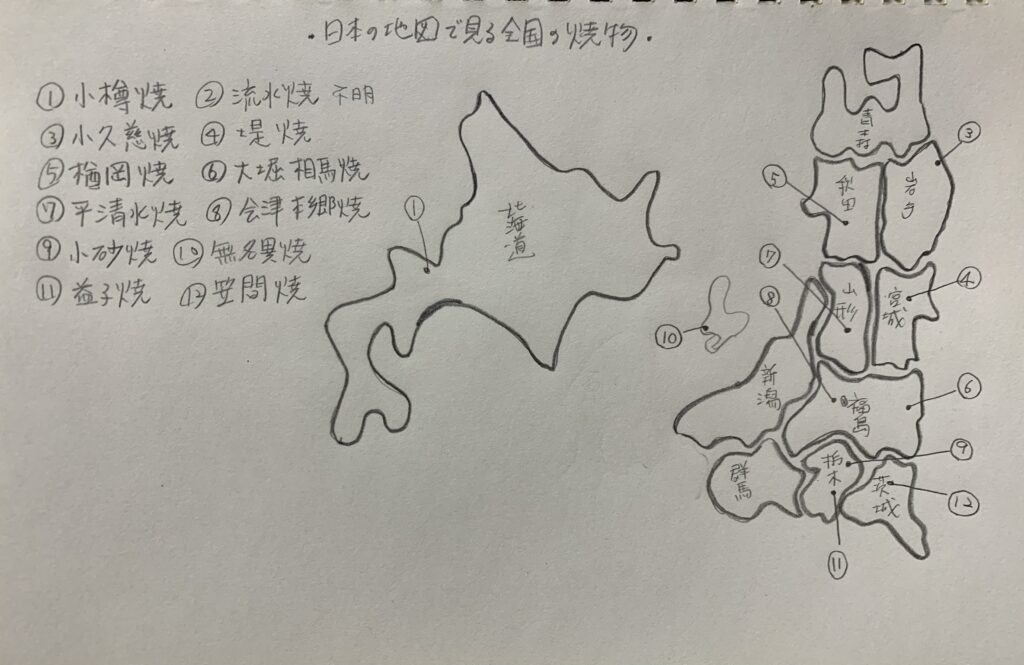
新潟県佐渡島相川地区
金山鉱山の開発に伴って成立した鉱山都市です。
2015年には、「佐渡相川の鉱山及び鉱山町の文化的景観」として、国の重要文化的景観に選定されました。
相川の町は標高300mの山地から海成段丘を経て、狭い海岸低地へとつながる地形をしています。
相川焼とは何について書いています。
相川焼の歴史は
1789年〜1800年に江戸後期に、黒沢金太郎が金太郎焼を創始したことから始まりました。
同時に、佐渡島相川地区の窯元を拠点に、無名異焼の焼成技術も発展していきました。
相川区は12の窯元と、人間国宝・伊藤赤水の窯元もあります。
相川焼の特徴・魅力は
釉薬を掛けなくても水が染み込まず、匂いもつきにくいです。
赤みのある煎茶器など、日用粗陶製品が多いのが特徴です。
高温で硬質に焼成されています。
1つも同じものがないといわれています。
成形後は、生の内に石や鉄ヘラなどで、磨いて光沢をだしていきます。
焼成後には、佐渡金山の精錬滓でさらに磨き光沢をだします。
焼き上がった器は、焼き締まっているので叩くと金属音を発します。
相川焼の土
佐渡の相川鉱山の土を原料です。
酸化鉄を多く含んだ赤土を使っています。
無名異土
陶芸家:伊藤窯一氏は、2003年に国の重要無形文化財保持者に認定されました。
相川焼の本物と偽物の見分け方は
本物は、
※ザラっとした質感
※光沢のムラ
※経年による変化
※職人の繊細なタッチ
※独特の絵柄の配置
※窯元や作家の裏印
本物を手に入れる方法としては、信頼できる専門店や、窯元から直接購入するのがおすすめです。
偽物は、
※均一の光沢
※不自然な艶
※絵柄が機械的
※手作業の温かみがない
※裏印が不明瞭
※偽装されている
偽物は、骨董市やフリマなどの不明確なところでは購入は避けたほうがいいです。
本物を手に入れたいのであれば、専門家などの信頼ができる人に見てもらうことが確実だと思います。
相川焼の今は
相川の町を中心に今でも約25軒ほどの窯元があります。
以上が、相川焼とは何でした。
まとめ
相川焼とは、赤みのある煎茶器など日用粗陶製品が多いのが特徴の焼物です。
相川焼といわれますが、無名異焼ともいわれていますし、佐渡焼ともいわれます。
無名異焼の焼成技術が使われています。
水簸と絹目を通すため、陶土より粒子が細かく収縮率が大きいです。
赤い色合いが目を引きますね。
本物を見にいきたいですね。
相川焼鑑賞の参考になれば嬉しいです。
最後まで見ていただきありがとうございます。
次回は、大谷焼とは何です。
アフィリエイト広告を利用しています。



コメント
金太郎焼について書かれていたので興味を魅かれて読みました。私は金太郎焼の蒐集と資料集めをしています。落ち着きと素朴な色合いに惹かれています。