
こんにちは、けいみるるです。
今回は、コテ・柄コテの使い方についてです。
コテ・柄コテという道具を知っていますか?
使い方は?
コテのイラスト図
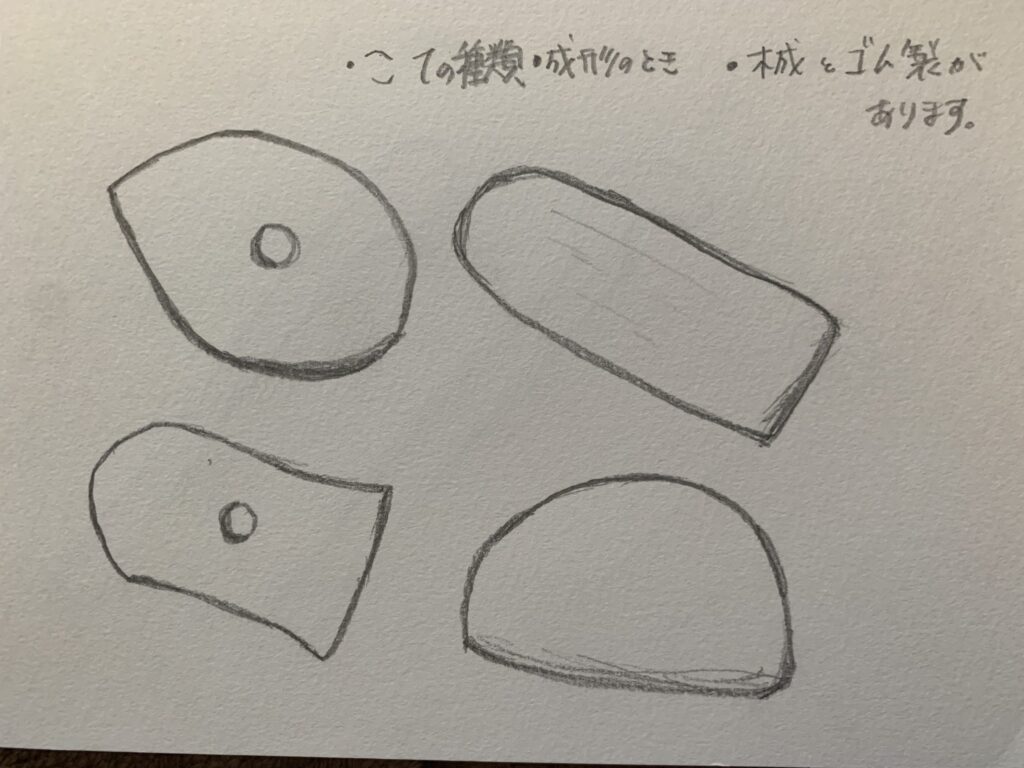
コテとは
成形の時に表面をなめらかにしたり、形を整えたりするのに使います。
種類は多数あります。
お皿・お茶碗・湯呑み・小鉢などに使います。
作品の内側の直線加工の際に使います。
粘土を締めるときにも使います。
アフィリエイト広告を利用しています。
成形:コテ・柄コテの使い方について書いていきます。
柄コテとは
柄コテのイラスト図
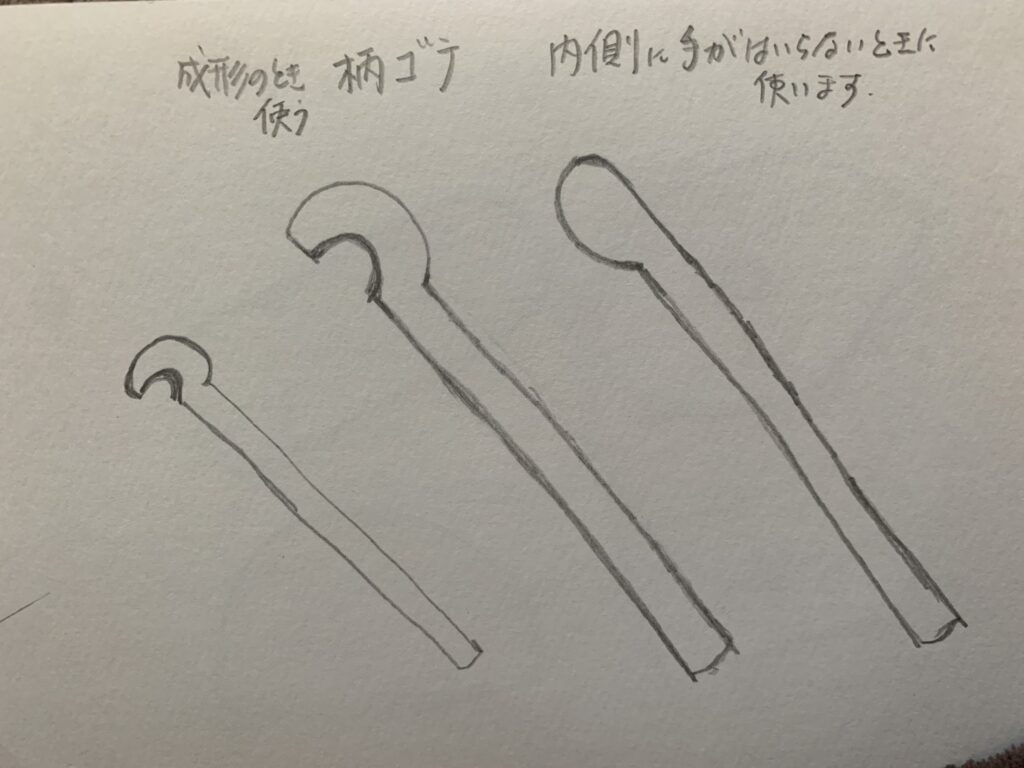
成形の祭に、作品の内側に手が届かない時に使います。
昔からある柄コテです。
大物の筒物に使います。
壺・かめ・花瓶・徳利などに使います。
アフィリエイト広告を利用しています。
コテ・柄コテのあて方・使い方は
コテのあて方
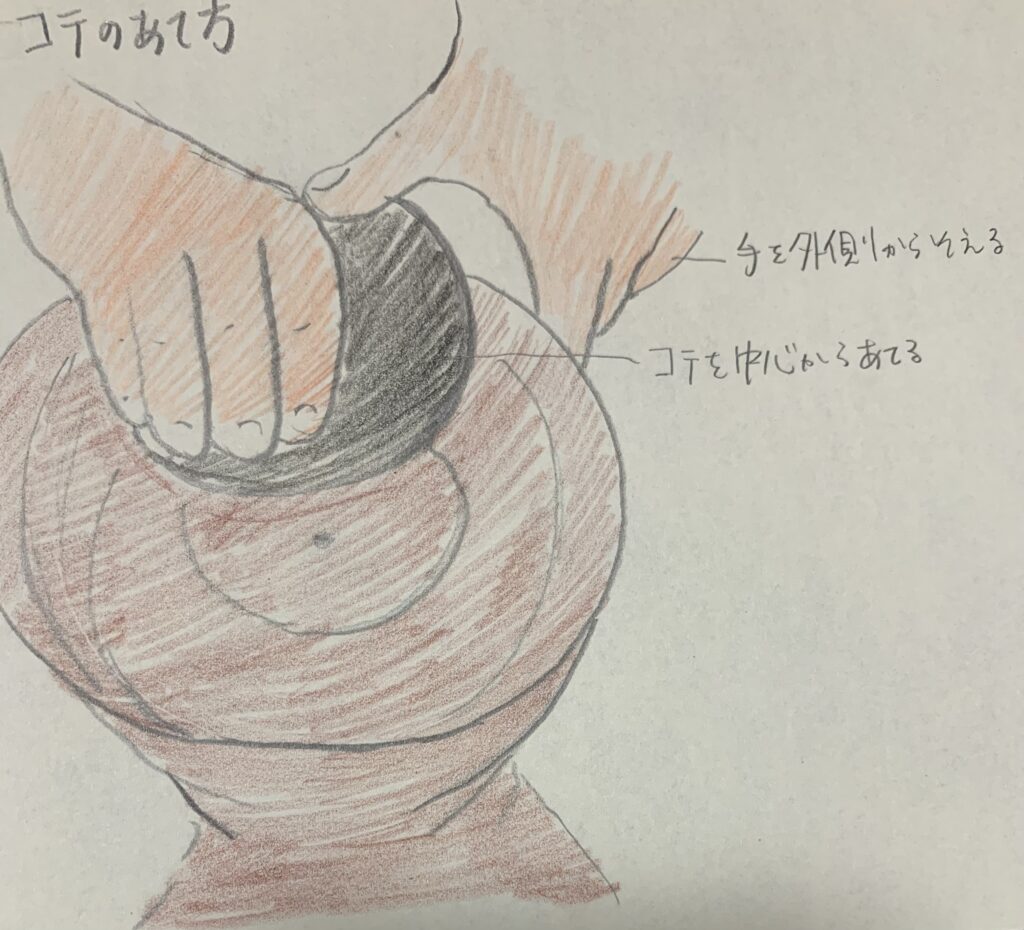
柄こてのあて方
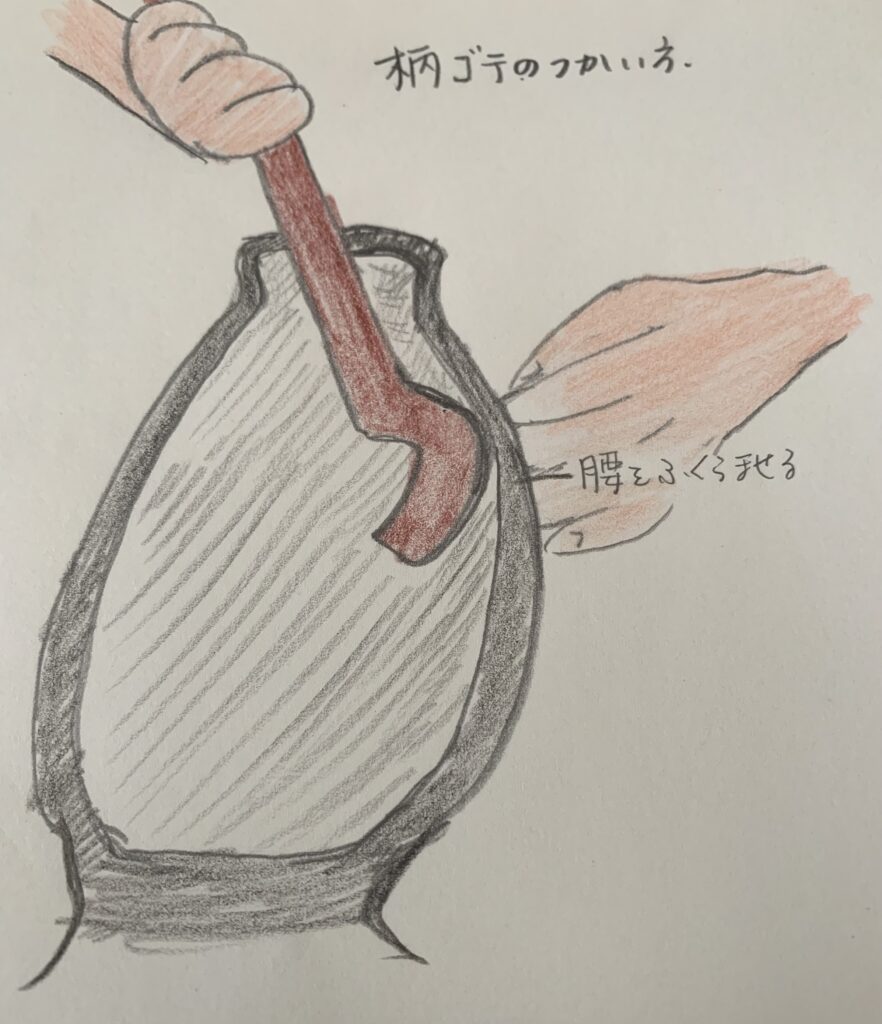
・底の中心にコテを持ってきて、横にスライドしていきます。
・腰の部分から外側からも手を添えながら、同時に口元まで引き上げていきます。
・手で粘土を上げるよりも、コテを使うことで粘土が引き上げやすくなります。
・底あてをすることで、底割れがしにくくなります。
以上が、陶芸・コテ・柄コテとはでした。
まとめ
成形:コテ・柄コテの使い方では、コテは、粘土を締めたり、広げたり、引き上げるのに使います。
ゴム・ステンレス・木製など種類はたくさんあります。
柄コテは、徳利・壺など手が入らないとき、胴を膨らませたり、ならしたりするのに使います。
手の代わりになる便利な道具です。
コテ・柄コテの使い方の、参考になればうれしいです。
最後まで見ていただきありがとうございます。
次回は、削り:掻きベラ・カンナとはです。
アフィリエイト広告を利用しています。
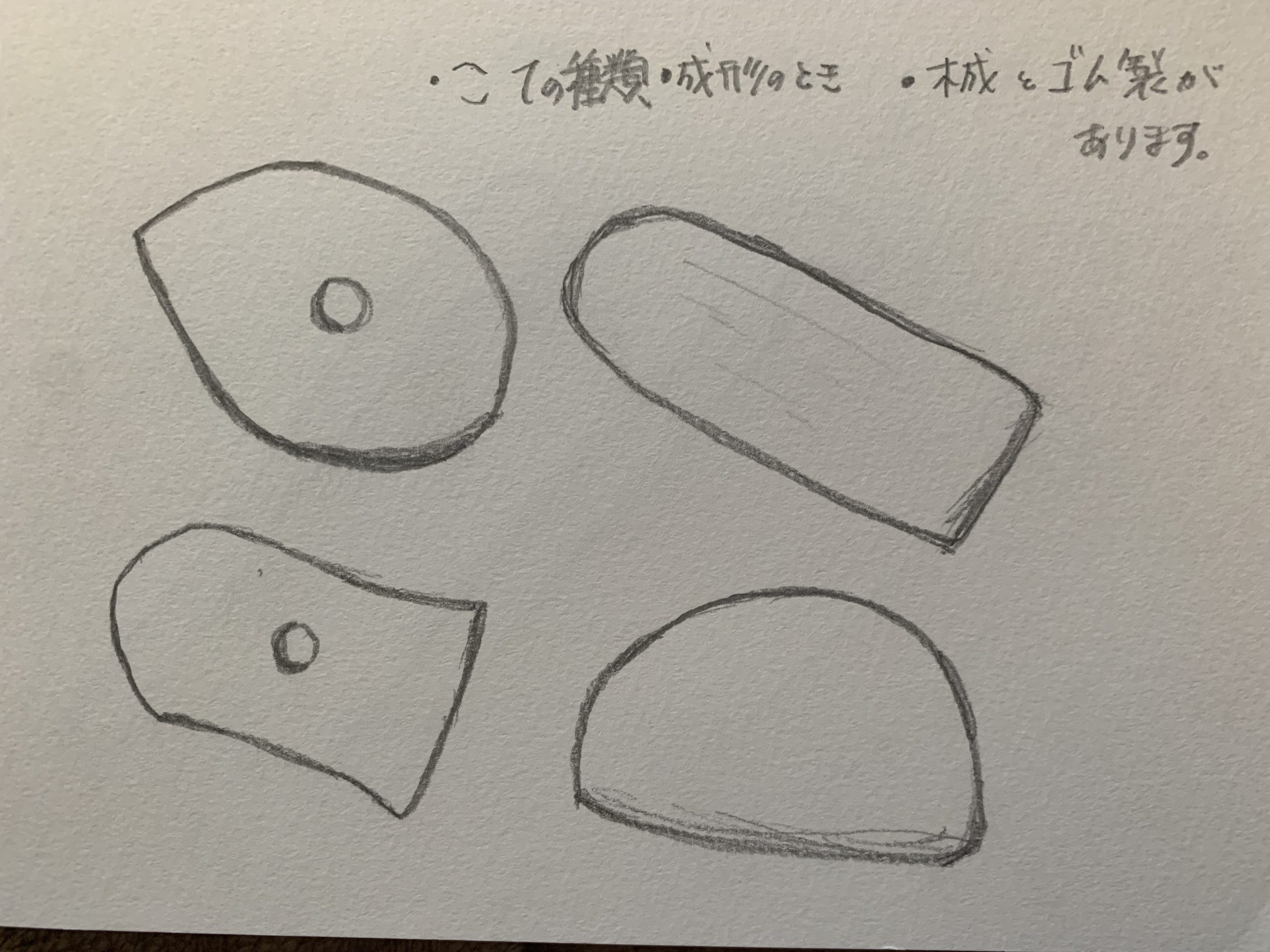



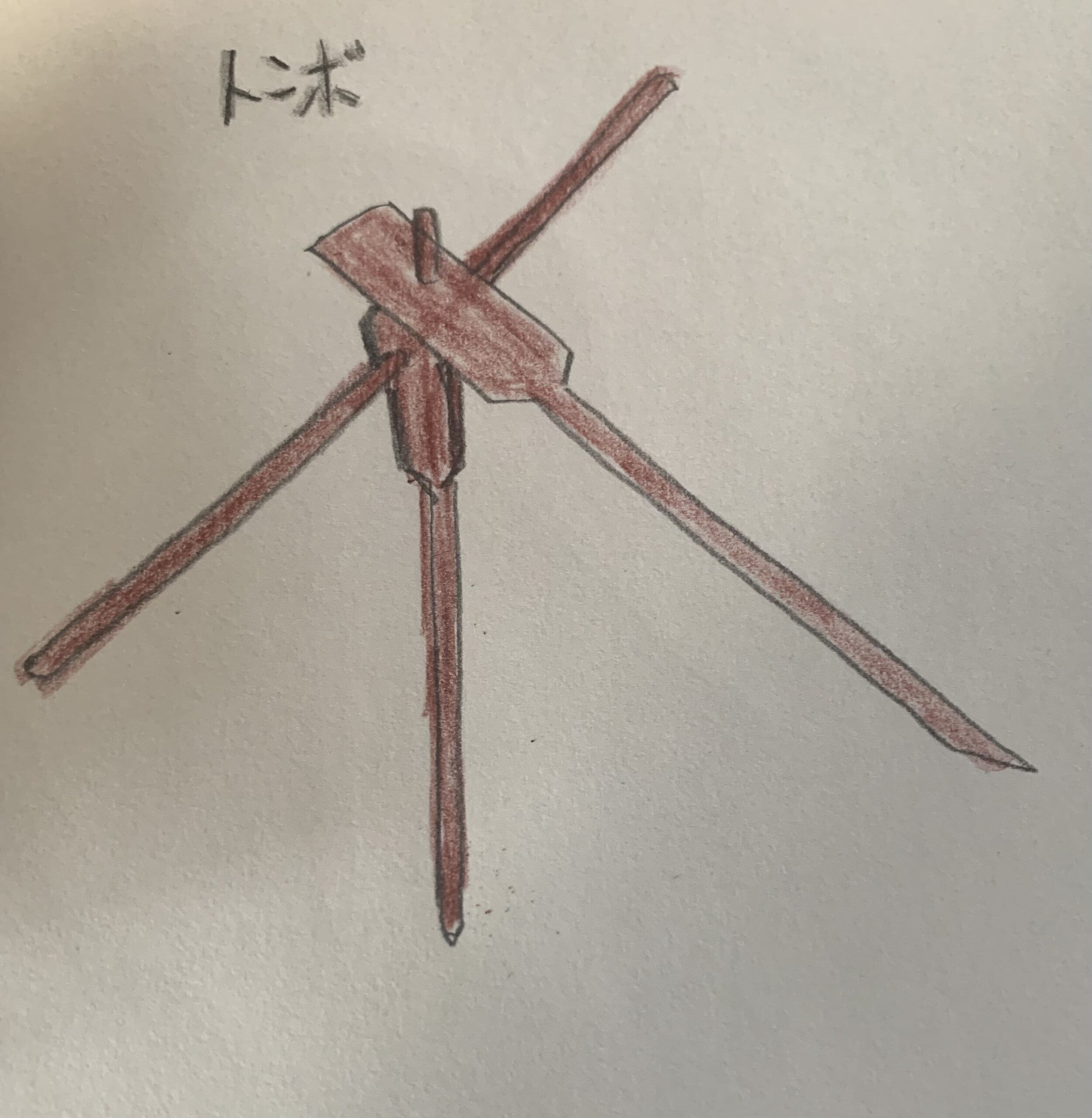
コメント