
こんにちは、けいみるるです。
今回は、片口小鉢の削り方についてです。
片口を付けた本体の削り

注ぎ口を半分に割って、本体に取り付けています。
片口小鉢の削りでは

片口を半分に切ります。
口元にあてて、取りつける部分を鉛筆で薄く線を書いておきます。
本体に、穴を丸く開ます。
片口小鉢の削り方を書いていきます。
片口小鉢の削り方のポイントは
*片口を本体に付けていきます。
*片口は、半分に切って、切った半分を使います。
*本体は、片口を合わせるところに、印をつけて付ける部分に穴をあけます。
*本体は、高台を削り、全体を軽くなるまで削ります。
片口小鉢の削り方は

ろくろに直接置いて、固定用粘土をつけています。
電動ろくろ
削り方は、器の削りてどうやるのを御覧ください。
片口小鉢の本体の削りの手順
①底の部分を削ります。
②高台を作ります。
③腰から口元まで軽くなるように削ります。
④高台は、輪高台です。
片口の半分の状態

片口のつける手順
①作っておいた片口を半分に切り離します。
②本体は片口をつける部分に、鉛筆で印を薄くつけます。
③本体に丸く穴を開ます。
④穴をあけた部分に、片口の半分を付けます。
⑤つけるときは、ドベを使って接着します。
⑥くっつけたら、取れないようにしっかり抑えます。
⑦細い棒で付けた部分を押し付けて取れないようにします。
⑧最後に、スポンジで全体をならします。
⑨底の部分に、陶印を押します。
以上が、片口小鉢の削りの完成です。
まとめ
片口小鉢は、小鉢に口が付いていることをいいます。
今回は、片口を別に作ってくっつけました。
半分に切り離して、微調節しながら本体に付けていきます。
取れないように、しっかり押し付けておきます。
その後に、細い棒でなでつけます。
ここが、ポイントになります。
参考になれば嬉しいです。
乾燥をしてから素焼きにしていきます。
次回は、片口小鉢の釉薬掛けです。
最後まで見ていただきありがとうございます。
アフィリエイト広告を利用しています。

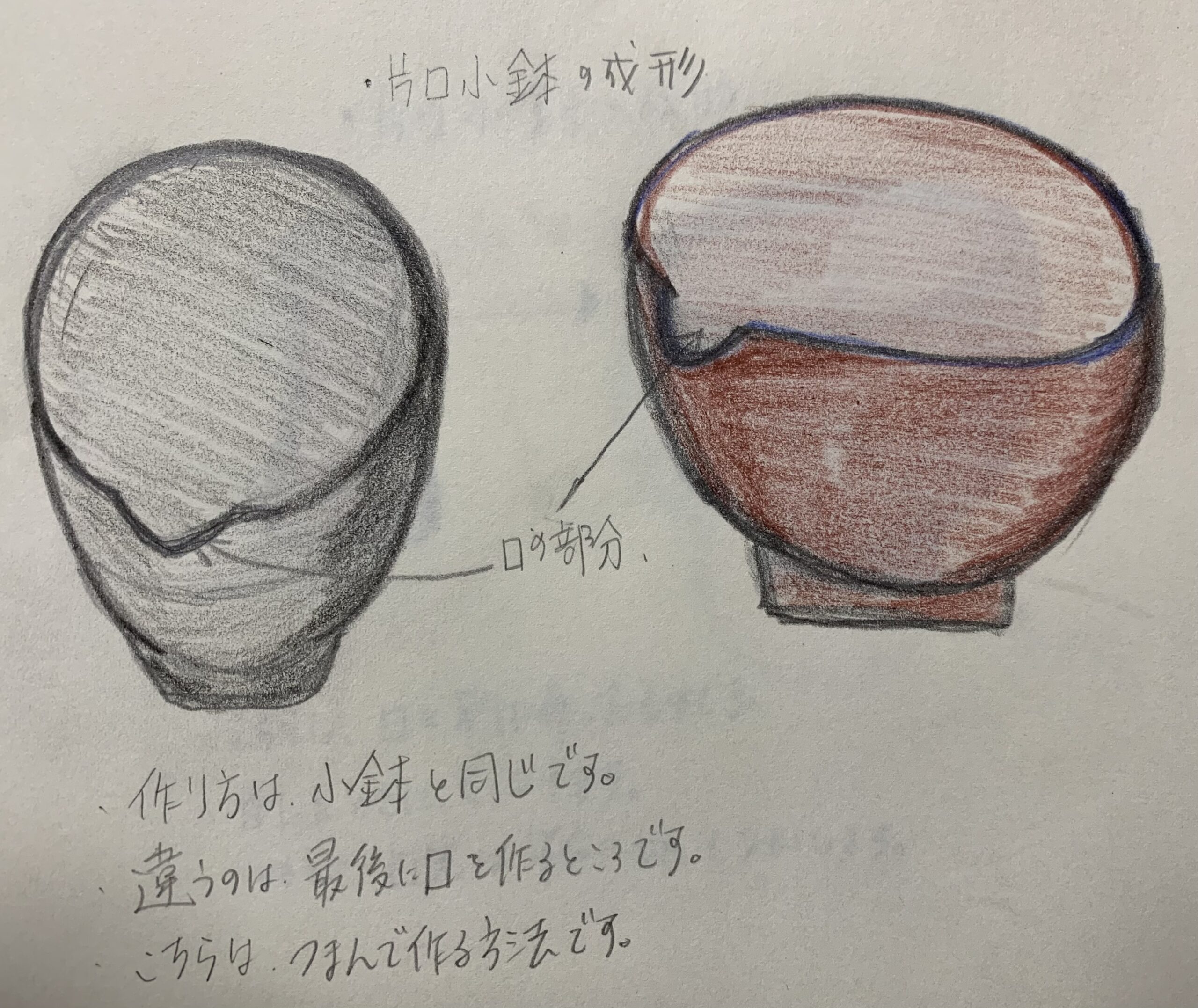

コメント