こんにちは、けいみるるです。
今回は、渥美焼とは何についてです。
渥美焼という焼物を知っていますか?
どこの地方の焼物でしょうか?
渥美焼の壺

渥美焼(あつみやき)とは
日本三大古窯の一つともいわれています。
落ち着きのある黒っぽさの焼き上がりが特徴です。
平安末期から鎌倉初期にかけて全盛期を迎えました。
東海地方

愛知県渥美半島に分布する古窯群です。
太平洋に面した長い海岸線渥美半島です。
農業・花の生産が盛んです。
渥美焼とは何について書いていきます。
渥美焼の見るポイントは
・土に鉄分が含まれているため、高温で焼かれると黒味を帯びたり、赤く変色したりします。
・遺跡から出土したものの中には、黒っぽい鉄分が斑点のように多数浮き出たものも見られます。
渥美焼の歴史は
猿投窯の影響を受け12世紀初頭に開窯しました。
平安時代から鎌倉初期にかけけ渥美半島には、伊勢神宮の神領や三河国の国衛領が置かれ、神宮の神官や中央の貴族の需要にこたえるとめに、陶器が盛んに作られていました。
これらを、渥美古窯とよんでいました。
豊橋市南西部から渥美半島の先端にかけて、100群600基を超える窯が築かれました。
平安時代末期の1181年に、東大寺が火事で消失し、鎌倉時代で再建されました。
このとき、瓦を焼いていたのが、渥美半島の先端にある国史跡・伊良湖東大寺瓦窯跡(しせき・いらごひがしだいじがようあと)です。
短期間で歴史の幕を閉じています。
渥美焼の特徴・魅力は
砂質粘土で成形し、焼き上がりは灰色・黒褐色で瀬戸焼、常滑焼とは違う長石の吹き出しはありません。
松の灰が高温で自然釉となり緑色になるのが特徴です。
蓮弁分壺(れんべんぶんつぼ)で代表される経筒容器があります。
燻製は焼成の最後に窯を密封して燻し(いぶし)、炭素を付着させて器面を固めます。
燻製は意図的な焼成ではなく、地域特有の窯構造により、自然燻製と同じ効果が現れたにすぎないといわれています。
高台がついたものは生産されなくなりました。
渥美焼の粘土
原料は、渥美半島の土です。
土は砂気が多く、焼き締まりは悪いです。
渥美焼の釉薬
灰釉が特徴です。
渥美焼の本物と偽物の見分け方
本物は
数百年使うことによって、無数の小さな傷が多方向についています。
釉薬の劣化により光沢が失われています。
職人に手仕事により、自然な歪みがみられます。
偽物は
不自然に水平に傷が入っていることが多いです。
不自然に光沢が強かったり、均一だったりします。
不自然な歪みがあります。
自分でできる本物と偽物の見分け方はこのようなことがいえます。
ですが、偽物は本物にそっくりに作られていますので、見極めるのは難しいと思います。
そんなときには、信頼のあるお店や、プロの鑑定士に見てもらうのが確実です。
渥美焼の今は
田原市皿焼古窯館として復元保存されています。
市の指定史跡に指定されています。
40年以上にわたり渥美焼の制作を続けてきた団体が、約半年間の休止を経て復活をしました。
以上が、渥美焼とは何でした。
まとめ
渥美焼は、愛知県渥美半島で焼かれた古窯群です。
日本三大古窯の一つに数えられます。
渥美の土は、砂気が多く、その分焼き締まりが悪いので一部で焼き方を工夫しています。
鉄分も多い渥美の土を使っていますので、濃い茶色・灰色・黒褐色の焼き上がりが特徴です。
早い時期に灰釉陶器の生産が軌道にのりました。
早い時期に、生産が途絶えました。
渥美焼という焼物があることを、初めて知りました。
歴史があるのに、あまり知られていないですね。
長く続かなかったのが残念ですね。
現在でも、作品が残っているのがすごいですね。
実物をみに行ってみたいです。
渥美焼鑑賞の参考になれば嬉しいです。
最後まで見ていただきありがとうございます。
次回は、台焼とは何についてです。
アフィリエイト広告を利用しています。
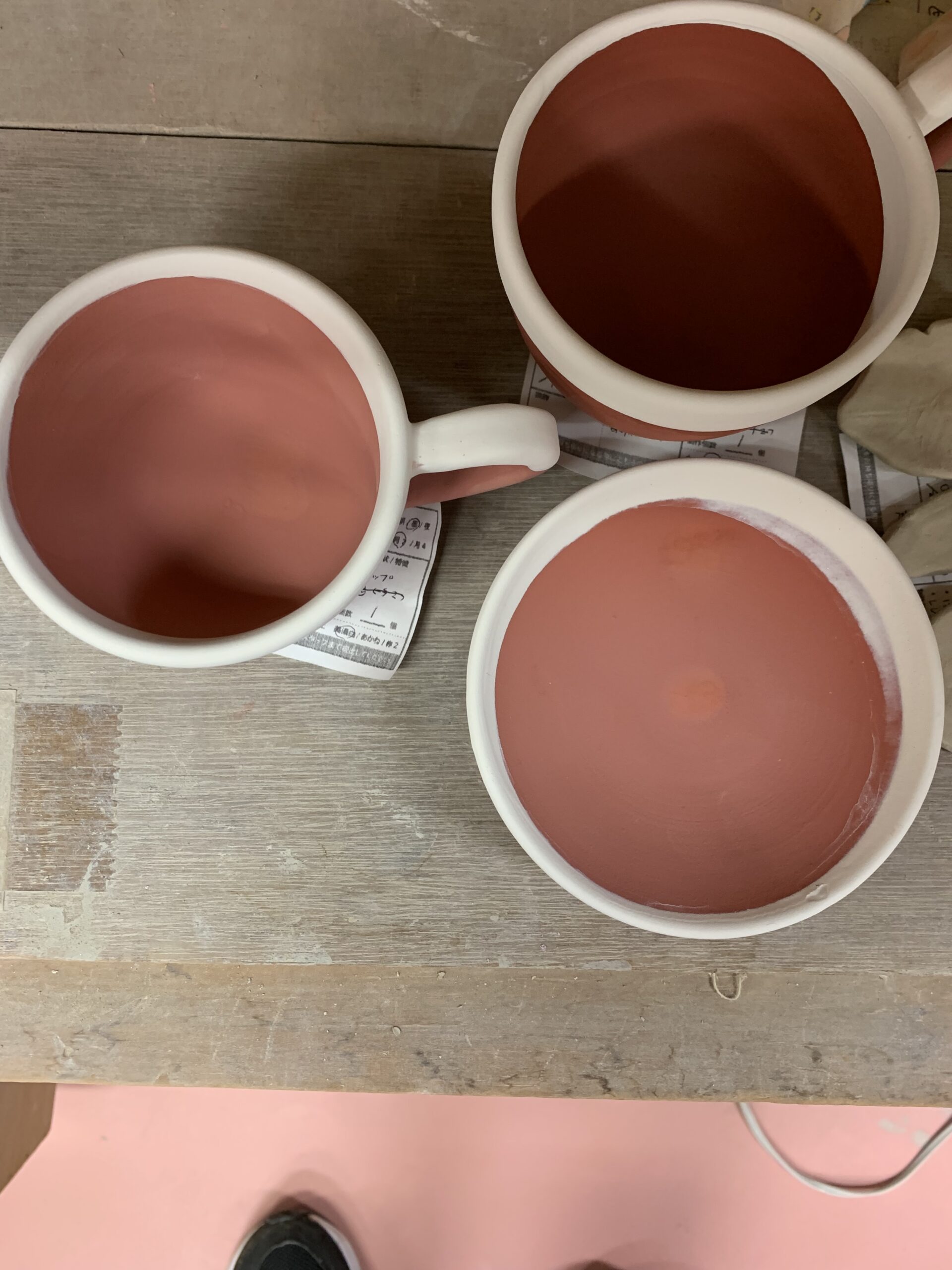

コメント