こんにちは、けいみるるです。
今回は、石見焼とは何についてです。
石見焼という焼物を知っていますか?
どこの地方の焼物でしょうか?

石見焼とは、
茶褐色・透明・黄土色・青色があります。
陶土が耐酸性で高温焼成が可能なので、耐酸・耐塩・耐水性に優れています。
中国地方
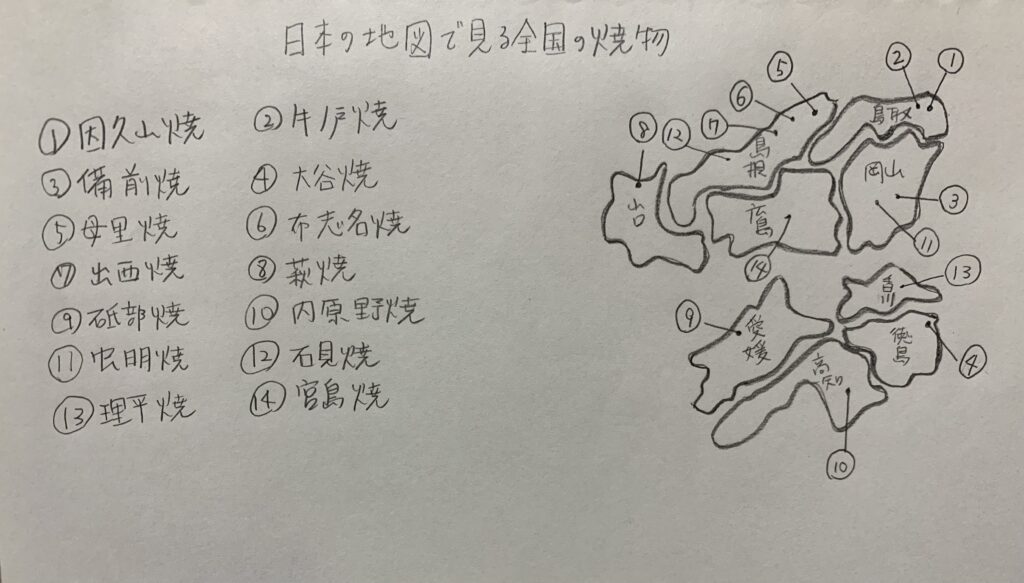
島根県江津市が中心ですが、浜田市・大田市でも焼かれています。
島根県は最も面積が狭い市です。
江の川と日本海、緑ある山野に囲まれた町です。
赤瓦が特徴的な日本三代瓦の一つ「石州瓦」の産地としても知られています。
石見焼とは何について書いていきます。
石見焼の見るポイントは
*耐酸・耐塩・耐水性に優れています。
*水かめだけではなく、灰皿なども多く作られています。
*完全燃焼した炎で焼くと黄土色をしています。
*不完全燃焼した炎で焼くと青色になります。
石見焼の歴史は
18世紀の中頃から島根県西部で焼かれ始めた陶器の総称です。
250年以上の歴史が長い焼物です。
1592年〜1610年頃に朝鮮の陶土が日本に連れて来られました。
その時に石見焼が始まったとされています。
1765年に、周防岩国藩から陶工を招き、片口や徳利などの小さい焼物がつくられるようになりました。
1994年7月には、国の伝統的工芸品に指定されました。
石見焼の特徴・魅力は
「はんどう」といわれる大型の水瓶(みずかめ)を明治時代に量産されました。
最盛期には、100軒を超える窯元があったといわれています。
大型陶器の焼物を支える石見焼の伝統的技法が「しの作り」です。
吸水性が低く強固で、塩分・酸・アルカリに強い素地です。
石見焼の粘土
磁器に近く、地元の土です。
地元の都野津層粘土が使われています。
石見焼の釉薬は
来待釉薬(きまちゆうやく):鉄分を含んだ深みある茶褐色をしています。
温泉津石(ゆのついし):アルカリを含んだ透明な釉薬です。
釉薬は、焼成の火加減で発色に違いがあります。
酸化焼成は黄土色に発色します。
還元焼成は青色に発色します。
原料には、益田長石・石灰石・わら灰・土灰などがあります。
粘土・釉薬はすべてが天然です。
石見焼の本物と偽物の見分け方
本物
非常に硬くて耐久性が高いです。
長期間使っても水漏れしにくく、匂いやあ色がつきにくいです。
上記に描かれていることです。
偽物
画一的な釉薬処理・機械的な模様になっているものです。
均一的で完璧な形状のものは、型で作られています。
偽物は、本物に近づけようとしています。
本物を見分けるのは、難しいですね。
石見焼の今は
窯元は今では、7軒あります。
後継者は、3軒です。
いまでも日用品など色々な器を作っています。
ガスや電気の窯を使っている窯元もある中、いまでも登り窯にこだわっている窯元もあります。
以上が、石見焼とは何でした。
まとめ
石見焼とは、吸水性が低く強固で、塩分・酸・アルカリに強い素地です。
水かめなど大きな壺を中心に制作されていました。
磁器に近い粘土で、地元の粘土を使っています。
伝統的な技法を今でも守り続けています。
特徴のある壺、昔からありますね。
よく漬物に使っているのをみたことがありますが、石見焼という名前は知りませんでした。
いつまでも残していきたいですね。
窯元巡り散策のお役に立てれば嬉しいです。
次回は、白石焼とは何です。
最後まで見ていただきありがとうございます。
アフィリエイト広告を利用しています。


コメント