こんにちは、けいみるるです。
今回は、真朱焼とは何についてです。
真朱焼という焼物を知っていますか?
真朱焼の湯呑み

白色と赤色の色合いもいいですね。

赤い色が輝いていますね。
真朱焼とは、
独特の赤、真朱釉が特徴です。
関東地方の地図のイラスト図
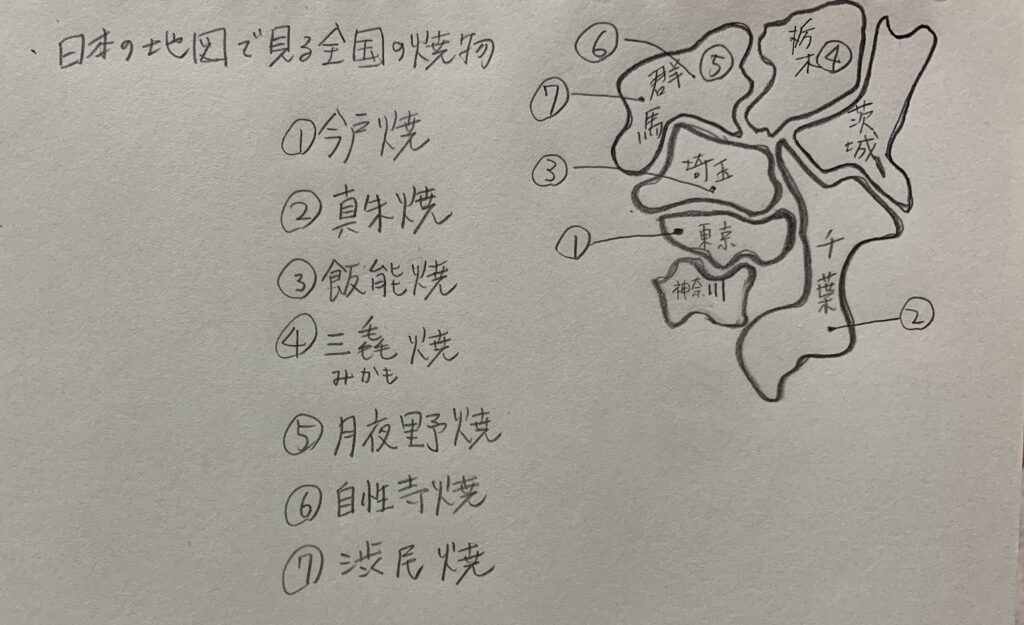
千葉県鎌ケ谷市で焼かれています。
鎌ケ谷市は、千葉市の北西部に位置すます。
都心から25km圏にあり、自然豊かです。
真朱焼とは何について書いていきます。
真朱焼(しんしゅやき)の見るポイントは
*真紅色が特徴です。
*昔の色は、朱色で、現代のような真っ赤ではないです。
*県の伝統的工芸品に指定されています。
真朱焼の歴史は
大正時代に陶芸家・濱田敬山氏(はまだけいざん)により、古代中国の経血焼(けいけつやき)を参考に市川市鬼超で始まったといわれています。
朱色の陶器です。
終戦後、鎌ケ谷の工芸品です。
サンゴのような真紅の陶器は、西洋人の間で人気となり昭和30年代末頃まで、アメリカ・カナダ・オーストラリアなど、海外に多く輸出品として生産されました。
平成では、約10年間郵政省の年賀はがき三等賞品とされたことから、国内でも広く知られるようになりました。
現在は、陶芸家の三橋英作氏が唯一の後継者といわれています。
70年と歴史は浅いです。
真朱焼の特徴・特徴は
燃えるような真紅色です。
つぼ・茶碗などが作られています。
昔は、ややくすんだ深みのある朱色のことで、万葉集ではこの色を「まそほ」と読んでいます。
真朱焼の今は
千葉県の伝統的工芸品に指定されています。
現在は、陶芸家・三橋英作氏が唯一の後継者といわれています。
以上が、真朱焼とは何でした。
まとめ
大正時代に陶芸家・濱田敬山氏によって市川市鬼越で開発された独自のもので、鬼越真朱焼と呼ばれています。
燃えるような真紅色が特徴です。
赤い色が、目を引きますね。
真っ赤な色がきれいに輝いていますね。
最後まで見ていただきありがとうございます。
次回は、高遠焼とは何です。
アフィリエイト広告を利用しています。


コメント