こんにちは、けいみるるです。
今回は、高遠焼とは何についてです。
高遠焼という焼物を知っていますか?
高遠焼の湯呑み

緑色と白色が印象的ですね。
高遠焼とは、
白い釉薬に緑の釉薬を掛けた2重掛けが特徴の焼物です。
北陸地方のイラスト図

長野県上伊那郡高遠町で焼かれています。
高遠町は高遠藩の城下町でした。
国指定史跡であり日本100名城の1つでもある高遠城があります。
現在は、桜の名所の公園となっています。
「天下第一の桜」といわれています。
高遠焼とは何について書いていきます。
高遠焼の歴史は
200年以上の歴史があります。
1812年高遠城内に水を引くために、土管を焼かせたのが始まりといわれています。
美濃の陶工を招いて作られています。
昭和の中頃には衰退していきました。
昭和50年代には唐木米之助(とうもくべいのすけ)という陶工が復活させました。
高遠焼の特徴・魅力は
特徴的なのは主に釉薬にあります。
地元で採れる粘土が赤土だったので、白色の釉薬が掛かった上に、緑色の釉薬を流しているものが多いです。
その他にも、黒色の釉薬の上に白色の釉薬が流してあるなど、釉薬を2重掛けしてあるものが多いのが特徴となっています。
赤土に白や緑などの釉薬を2重掛けした色合いです。
手の跡を残したような形や、口の部分が厚手のものが多いです。
田舎風の素朴な味を持つ焼物として、多くの人々にひたしまれています。
昔からの色でいうと青緑色のものが一般的でした。
今は、高遠の桜をイメージしたピンク色の釉薬を使って色をだしています。
高遠焼の今は
高遠焼きの粘土は、採りきってしまったため、今ではあまり採れなくなりました。
今取れる粘土は耐火度が低いので、高遠の粘土と他の似たような粘土を混ぜて使っています。
現在では、灯油窯と併用して登り窯を使っています。
登り窯は、4部屋をつかっています。
以上が、高遠焼でした。
まとめ
高遠焼とは、赤土を基調とした、白色と緑色など2種類の釉薬を重ねる「2重掛け」が特徴となります。
聞いたことがなかった高遠焼です。
緑色が印象的な釉薬ですね。
高遠焼きの実物を見てみたいですね。
散策の参考になれば嬉しいです。
最後まで見ていただきありがとうございます。
次回は、織部焼とは何です。
アフィリエイト広告を利用しています。

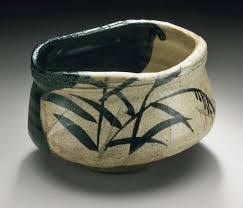
コメント