こんにちは、けいみるるです。
今回は、飯能焼とは何についてです。
飯能焼という焼物を知ってますか?
どこの地方の焼物でしょうか?
飯能焼の器

*飯能焼とは、
真能寺村原の窯場で焼かれていました。
*耐火性の強い、薄手の器です。
*色が白く可塑性(かそせい)の少ない粘土です。
関東地方
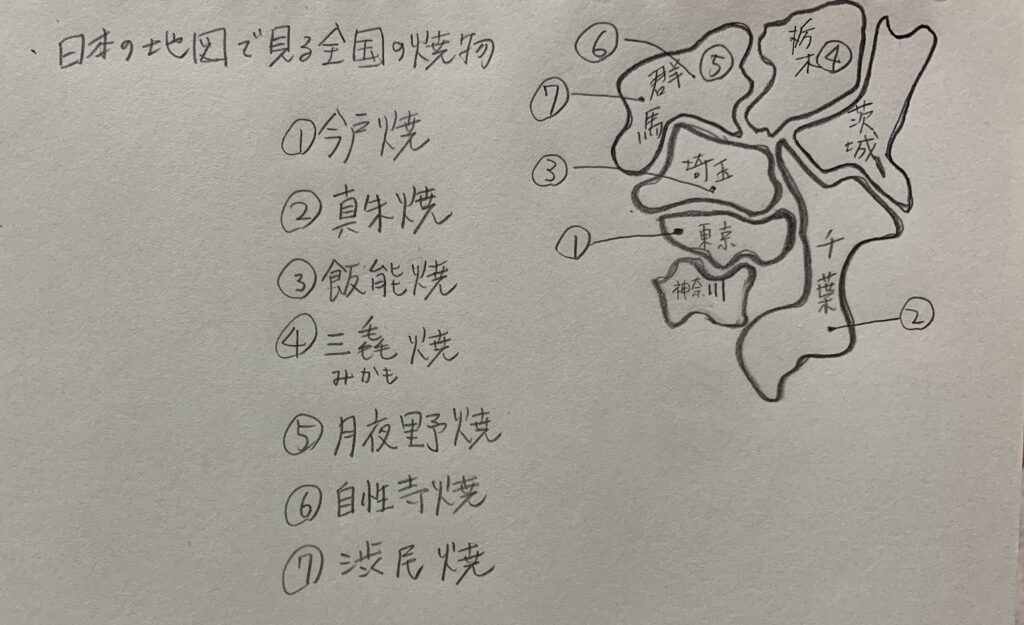
埼玉県飯能市の原町周辺で焼かれています。
飯能市は埼玉県の南西部に位置しています。
市域の7割以上が森林が締める自然が残る地域です。
飯能焼とは何を書いていきます。
飯能焼の見るポイントは
*鉄分の多い土に、白絵土によるイッチン描きの絵付けです。
*青い色の釉薬が魅力的です。
*耐火性の強い日常雑器が作られています。
*すすきの絵柄が多くあります。
飯能焼きの歴史は
1832年に、真能寺村原の窯場で1887年まで開窯していました。
約50年間焼かれていました。
名主・双木清吉(そうもくせいきち)が信楽の陶工を招き開窯しました。
益子焼・笠間焼と並び関東の名窯といわれていました。
明治20年に廃窯しました。
飯能焼の特徴・魅力は
鉄分の多い土に、白絵土によるイッチン描きの絵付けがされています。
粘土には鉄分が多くあるため、濃い緑褐色の釉薬と絵付けがあります。
耐火性の強い日常使いが中心です。
薄手の器です。
飯能焼の粘土は
山採りの原土から粘土を作る整備を有する数少ない窯元です。
100%の飯能土です。
鉄分が多く濃い緑褐色をしています。
飯能焼の釉薬は
釉薬も飯能の草木の灰を使っています。
独自に配合した釉薬が使われています。
古飯能焼では、釉薬が緑色を帯びた褐色のものが多いです。
新しい作風、飯能ブルーといわれる翠青磁を中心に焼かれています。
飯能焼の今は
現在は、2軒のみの窯元があります。
以上が、飯能焼とは何でした。
まとめ
飯能焼とは、埼玉県飯能市で焼かれている焼物です。
耐火性の強い日常雑器が中心で、薄手の器になっています。
青いの釉薬が特徴です。
今でも、伝統を守りながら、現代にあった作品を作り続けています。
散策の参考になれば嬉しいです。
最後まで見ていただきありがとうございます。
次回は、渋民焼とは何です。
アフィリエイト広告を利用しています。


コメント