
こんににちは、けいみるるです。
今回は、中鉢・大鉢の作り方についてです。
小鉢よりも大きい器です。
中鉢を作ってみましたが、縮むのでどのくらいの大きさに焼き上がるかはわかりません。
大鉢は大きいのでいつか作れたらと思います。
中鉢・大鉢イラスト絵図
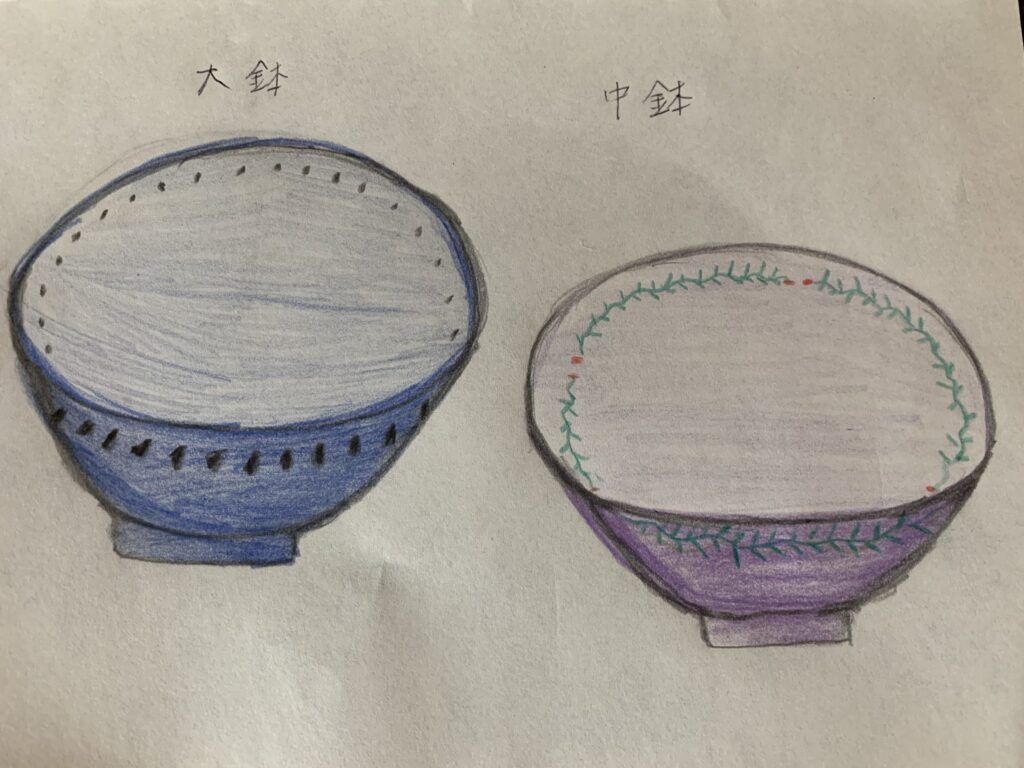
中鉢
上から

口元を変えてみました。

中鉢とは
預け鉢とも呼ばれています。
直径12cm〜21cmで、深さは4cm〜6cm、くらいの大きさです。
大鉢とは
大きな鉢のことです。
21cm以上のものです。
和え物や炊き合せなどおかずとして、食べれる物を入れます。
食事の時に、煮物・サラダ・酢の物など、たくさん盛り付けるのに使われます。
アフィリエイト広告を利用しています。

中鉢・大鉢の作り方を書いていきます。
中鉢・大鉢の作るポイントは
※大鉢のバイイは、ろくろに亀板を固定します。
※中鉢ならまだ亀板がなくても外せました。
※好みの大きさの粘土の塊を亀板の中心に置きます。
※内側の中心から横に広げていきます。
※木コテを使い広げたり、指跡を消したりします。
大鉢・中鉢の作り方は
電動ろくろ
成形の仕方については、器の作り方・成形とはを御覧ください。
水を入れた容器・スポンジ・なめし皮・切り糸・コテ・濡れたタオル・電動ろくろ・亀板です。
粘土はそれぞれ中鉢は1kgくらい、大鉢は1.5kgくらいです。
大鉢・中鉢の作り方の手順
①中心から粘土を広げていきます。
②両手の人差し指・中指・薬指を使って上げていきます。
③底の形を決めます。
④1cm〜2cm位底の厚みを取ります。
*ここまでは、中鉢も大鉢も作り方は同じです。
⑤底は平らで徐々に斜めに上げていきます。
⑥深鉢・浅鉢で高さが違います。
⑦形や厚みの調整には、コテを使います。
⑧コテを使うと、広げることもできます。
⑨広げるときには、外側も手を添えます。
⑩広がりすぎないように、もう片方の手で抑えます。
⑪形がきまったら、口元をなめし皮で整えます。
⑫縁の所に角をつけるのも、そのままでも花びらにするのもお好みです。
⑬底を切り糸で切ります。
亀板にのせたまま乾燥させます。
以上が、中鉢・大鉢の作り方でした。
まとめ
これが中鉢・大鉢の基本の作り方です。
底が深いもので、色々なおかずを入れられます。
形も大きさも多数あり、使い勝手がいいです。
慣れてきたら、自分の作りたい大きさの鉢を作るのもいいですね。
自分の作った鉢でおかずを入れて食べるのも、また一段と美味しいのではないでしょうか?
中鉢。・大鉢を作るときの参考になれば嬉しいです。
最後まで見ていただきありがとうございました。
次回は、中鉢の削り方です。
アフィリエイト広告を利用しています。
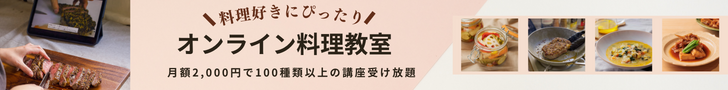
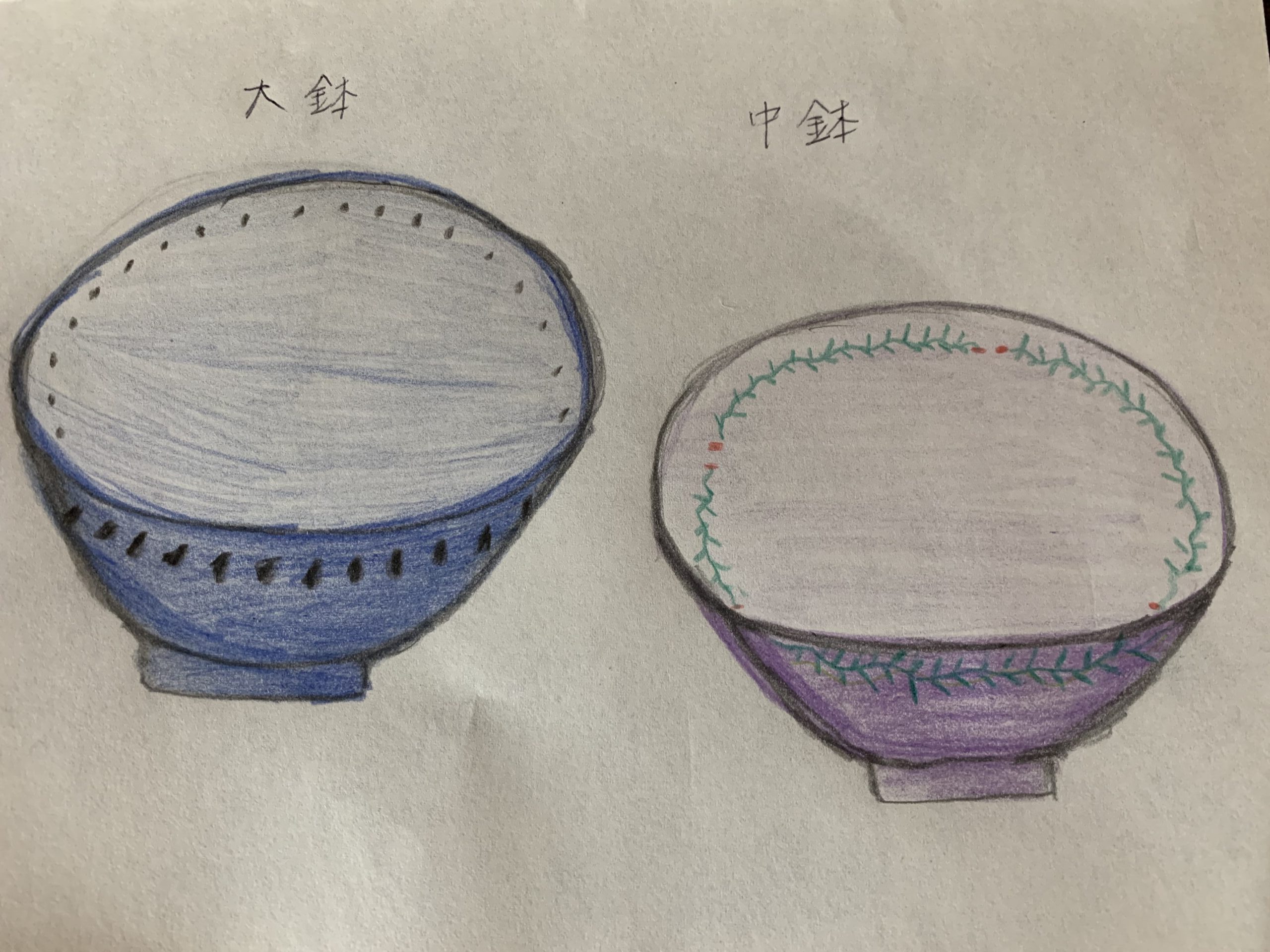


コメント