こんにちは、けいみるるです。
今回は台湾の焼物とはどんな焼物かについてです。
台湾の焼物てどんな焼物か知っていますか?
台湾の焼物

エビの絵付けが印象的ですね。
鶯歌陶瓷老街の街並み

台湾の焼物は、鶯歌陶は200年以上前から陶磁器は作られていました。
全国的にも有名であり、中国の景徳鎮ともいわれています。
陶磁器産業の重要地区であります。
台湾の焼物とはどんな焼物かについて書いていきます。
台湾の焼物の歴史は
台湾の陶磁器のルーツは砥部焼です。
戦前に台湾で広く流通していたからです。
淡水丈囲の工場から始まったのが「大同磁器」です。
台湾の磁器産業に大きくリードしてきました。
60年にわたって庶民の暮らしを支えてきました。
第二次世界大戦後、台湾が祖国に復帰して間もない頃には、陶器しかなく磁器はありませんでした。
技術も原料もなかったからです。
台湾には新北市にある「鶯歌老街」という、陶器の町があります。
陶器といえば鶯歌と言われるくらい有名です。
陶器の町となったのは清時代嘉慶期(1796〜1820)に呉岸・呉糖・呉曽らが、鶯歌に来た際に近くの尖山(とが)地区で良質な粘土がありそれを利用して、焼窯を築いたのが始まりと言われています。
2000年には「鶯歌陶瓷老街」という名が付けられました。
この付近には、大漢渓という川が流れています。
台湾の焼物の特徴は
ここでは、良質な粘土・石炭・薪があり水上交通という地の利で陶器が発展したのです。
鶯歌老街というところは、陶器のお店が非常に多くあるようです。
とても、歴史のある、古い町のようです。
お土産としても、実用的なものから、高級なものまで多種多様な陶磁器があります。
陶土と磁土を顔料として使っていますので、様々な釉薬を施して作られています。
青花磁や紅釉磁など、多様な装飾技法が使われています。
伝統を守りながら、現代にあったデザインで作られています。
実用性だけではなく、デザイン性も重視しています。
色絵磁器には、美しさと実用性が兼ね備えられた作品として知られています。
台湾のデザート皿は、深さと大きさが特徴です。
新北市鶯歌陶器博物館
台湾の陶芸文化の歴史を見ることができます。
以上が、台湾の焼物とはどんな焼物でした。
まとめ
台湾の陶芸は「鶯歌老街」とところが有名なのですね。
カラフルな食器もありますね。
エビの絵付けがいいですね。
焼物の歴史はあまり古くはないのだと感じがします。
街自体は歴史があるようです。
古い建物もありますね。
台湾は映像や写真でしか見たことないですので、いつか行ってみたいです。
私もこのような作品が作れたらと思いながら、日々陶芸のことを考えています。
日本の焼物もいいですが、台湾の焼物にも色々な形や色合いがあり魅力的です。
台湾陶器鑑賞の参考になれば嬉しいです。
最後まで見ていただきありがとうございます。
次回は、東南アジアの焼物とはどんな焼物かです。
アフィリエイト広告を利用しています。

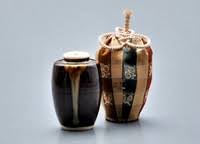
コメント