こんにちは、けいみるるです。
今回は、女流陶芸家・太田垣蓮月の生涯についてです。
太田垣蓮月
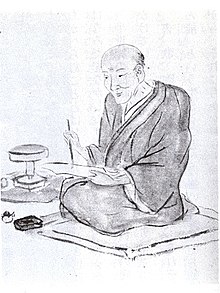
この時代には、女性の陶芸家はいたのでしょうか?
この時代には、男性しかいなかったのでしょうか?
この時代にいたのは、ただ一人の女性陶芸家・太田垣蓮月です。
江戸時代にいた女性陶芸家・太田垣蓮月を書いていきます。
江戸時代の陶芸家
女性編
「太田垣蓮月(おおたがきれんつき)」という女流陶芸家です。
幕末の時代に生きた、僧侶で歌人・陶芸家です。
京都に生まれます。
元の名は誠(まぶ)といい、蓮月は法名です。
太田垣光古(てるひさ)の養女です。
蓮月は明治8年12月10日に亡くなりました。
85歳でした。
蓮月は一度結婚しますが、夫と子と死別してしまいます。
その後出家しました。
養父の死後を機に、生まれ育った、知恩院を去って岡崎村を去ります。
住居を転々としていたことから、屋越し蓮月と呼ばれるほど引っ越しの多いことで、知られていました。
蓮月は陶芸で生計をたてていました。
蓮月焼という焼物を作っていました。
歌人でもありますので、自詠(じえい)の和歌を釘彫りで、施した作品のことを、 蓮月焼といわれています。
京土産として人気があり、評判も良かったことから、贋作が出回るほどでした。
蓮月焼の特徴は、自詠の和歌で製品を飾ったことです。
作品一つ一つに和歌を彫ってあります。
煎器関係が多いことと、てづくねや型を使って作陶していました。
洛東(らくとう)の粘土を買ったことです。
無釉薬と施釉薬の作品があります。
作品は茶碗・急須・ぐい呑み・茶の道具などがあります。
とても、才能に溢れた方だったんですね。
波乱万丈な人生を送っていたようです。
旦那さんやお子さんを亡くされても強く生きていた女性ですね。
陶芸だけではなく、歌人としても、活躍されていました。
江戸の京都の女流歌人、貞心尼(ていしんに)、千代女(ちよじょ)に並ぶ、三大女流歌人のひとりでした。
あまりの人気ぶりで焼物の注文が、ひっきりなしにつづいたことで、嫌になって逃げ出したそうです。
多いときには1年で13回も引っ越したそうです。
以上が、大田垣蓮月とはでした。
まとめ
太田垣蓮月は初めて知りました。
とても強い女性ですね。
この時代にも、一人の女流陶芸家がいたことに驚きました。
その他にもいなかったのかと、調べました。
他には、女流陶芸家はいないようです。
大変な時代に一人で生きていたなんて、すごいのひとことです。
最後まで見ていただきありがとうございます。
次回は、陶芸家の妻・板谷まるの生涯です。
アフィリエイト広告を利用しています。

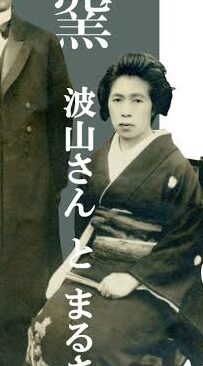
コメント